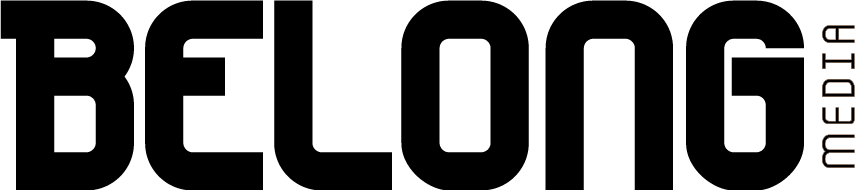最終更新: 2020年10月27日

(海外のレコーディング現場は)コツとかを言語化してないんじゃないかな。それはもう土地にあるというか、彼らの経験の中に培われてるようなところだと思うんですけどね。
アーティスト:後藤正文(Vo.,Gt)、喜多建介(Gt,Vo.)、山田貴洋(Ba)、伊地知潔(Dr) インタビュアー:yabori
-今回のシングルはどうして海外でレコーディングしようと思ったのでしょうか。
喜多:前からゴッチが海外レコーディングがしたいと言っていて、前のアルバムで2曲だけニューヨークでレコーディングをさせてもらって。海外のスタジオでやるだけで気持ちが違うというか。もちろん湿度とかも違うんだけど。
-今作のレコーディングはアメリカのデイヴ・グロールのスタジオでレコーディングしたそうですね。デイヴのプライベートスタジオはいかがでしたか?
後藤:めちゃくちゃ広かったですね。ロサンゼルスの郊外なので、とにかく天井は高いし、スタジオが広いからドラムの鳴りがすごくいい。アンビエントというか、スタジオ自体に独自のリバーブ感があって。それだけでアガりました。
-そうですね、ドラムの音がかっこよかったです。
後藤:海外に行くとドラムの音が良いんだよね。前に行ったニューヨークも良かったし。空気が乾いてるっていうのもあるけど、そういう環境で楽器自体がエイジングされてきてるからだと思う。日本のドラムと比べてどういう訳か音が良いんですよ。
-音が立体的ですよね。
後藤:今回はあまりコンプレッサーをほとんどかけないっていう話だったので、音がつぶれてないのは、ミックスエンジニアの腕によるところだと思うんだけど。
-ミックスのエンジニアの方がASHの『MELTDOWN』を手掛けたニック・ラスカリネクスだそうですね。どうして彼と一緒にやろうと思ったのでしょうか。
後藤:僕しか会ってないけど、すごいユニークな人でした(笑)。Foo Fighters側の推薦というのもあったんだけど、他にも候補があった中でちょうどニックの体が空いてるっていうことで、1曲「Easter」を試しにやってもらって。思ったよりラウドに上がってきてびっくりしたけど、いつも通り自分達の言う事を叶えてくれるエンジニアに意見を言うよりは、向こうの流儀に投げてみるのもおもしろいと思って。いつも通りのアジカンを海外へ行ってまで作っても仕方ないし。あと、ASHのTimに聞いたら「ロックでゴキゲンな奴だよ」っていうことだったから、(彼に頼んだら)いいかなって。
-意見の対立はなかったですか?
後藤:「Easter」のファーストミックスが来た時に要望を多めに送ったら、ニックのかけたエフェクトが全部切られたような、そのままの音が送り返されてきて。これは伝え方を考えないとマズイな、と(笑)。そこで、みんなの意見は集めるけど、ニックとのやりとりは自分にまかせてほしいって言って。翻訳されて伝わることなので、どう書いたら正しい訳につながるかなって考えてメールをしましたね。あとはもう会うしかないと思って。もともと、俺は直接行くべきだって話しをしてたんだけど、そのスッピンで返ってきたファイルを聴いて、マネジメント側もようやく、直接行く必要性が分かったみたいで。ニックの「だったらやらねぇ」みたいなセカンド・ミックスがあったおかげで(笑)。それによって会えたんだけど。
-皆さんにお聞きしたいのですが、海外と日本とのレコーディングの違いは具体的にどの部分にありましたか?
後藤:現地のスタッフはギターとドラムのことがすごく好きなんだなと思いましたよ。ベースの事を何も言わなかったし、ドラムとギターがとにかく好きみたい。リズム録りが終わってギターレコーディングが始まった時に、スタッフみんなが嬉嬉として口出してきたもんね(笑)。ギターについては、どこに秘訣があるのかって尋ねてみたけど、曖昧な事しか言わないんだよね。「リラックスして弾けば大丈夫だ」みたいなことしか言わないの。コツとかを言語化してないんじゃないかな。それはもう土地にあるというか、彼らの経験の中に培われてるようなところだと思うんですけどね。
伊地知:ドラムに関しては、日本では小さいスピーカーでチェックをするんだけど、いきなり大きなスピーカーで音を作ってて。良く聴こえるといえば聴こえるんだけど、音録ってチェックするときもそのスピーカーっていう。これは完全に文化の違いだなと思います。
後藤:うるさいから何も聴こえないのかなと思いきや、音の強弱を気にしてて。コンプレッサーもかけない。コンプレッサーをかけると、小さい音と大きい音の差がなくなって弱く叩いてる音も大きくなるんだけれど。リバーブについても、スタジオが十分に鳴ってるから、かける必要がないって言ってたり。かといって、根性論というわけでもない。技術として、そういうやり方を選んでる。多くの日本人は精神論や純血性にこだわっちゃうけど、彼らはプロセスよりも結果として音が良ければいいっていう。でもこだわるところはすごくこだわっていて、チューニングが合ってないっていうことや倍音が揃わないことについては30分くらいかけて調整したり。音がよく鳴ってるかどうかに対しては、とても気をつかってる。だけど、日本と海外で何が違うか一般化して語るのは難しいよね。ニューヨークとロサンゼルスでも違うと思ったし。あとは、その人の出身地によっても良い音に対する文脈が違うんじゃないですかね。俺たちは今回、思いっきりロサンゼルスの、いわゆるアメリカンロックやグランジ、オルタナ界隈の人達とやってるから。ニューヨークでもいろいろあるだろうしね、俺達が前に一緒にやったエンジニアはワシントンDC出身のハードコアシーンにいた人だったし。
-シングルの「Easter」からは原点回帰しようとする強い意志が感じられます。どうして今一度、原点に戻ろうと思ったのでしょうか。
後藤:原点感、そんなにないよね。ラウドなだけな気もするんだけどな。エモーショナルな曲を作りたいっていうのは話してたけどね。『崩壊アンプリファー』や『君繋ファイブエム』の楽曲よりは、構成もシンプルになってるし。ざっくり言うと、アメリカのロックを意識はしていたけど、サウンドシティ直系のラウドなサウンドを想像して制作をはじめました。
-今作のインタビューでは、シーンのど真ん中を目指すとありましたね。アジカンは十分過ぎるほど知名度があるし、シーンの真ん中にいるバンドだと思います。それにも関わらず、どうして今一度、真ん中を目指すと宣言したのでしょうか。
後藤:自分達の憧れていたロックの系譜の、その流れの川下にいることを意識した音楽を作りたいとは思っていて。まずは久々に正統派な8ビートをやりたいねって話はしたよね。2拍と4拍にスネアがはいってくるような、それが一番難しくて。
-シンプルだからこそ難しい?
後藤:ダサくなってしまうんですよ。自分達でここまでやってきて思うのは、四つ打ちだとキックでスペースが埋まって曲の推進力が増すし、リフのやり口も増えるというか、シンコペーションもしやすくなるんですよ。単純に気持ち良いっていうのもあるしね。だからこそ流行ってるんですけど。シンプルな8ビートは使い古されてるから、出し尽くされている感もあって。その上で新しいことをやるのは難しいけど、出来たら楽しいし、そういうことに挑戦した方が面白いかなと思うので。正統派の8ビートって減ってきているような気もするし。潔もその中に工夫があったりとか、ベースもルートからの外れ方とか、山ちゃんならではのところもあるし。いろんな挑戦もしながらですけど。
-王道の8ビートへの挑戦っていう意味合いも強かったんですか?
後藤:今回は四分キックはなしだよねって話はしたよね。
伊地知:『ファンクラブ』の時は8ビート禁止だったんです。2拍,4拍にはスネアを入れないでって言われてたんですけど。それが今一転してこうなってる。
後藤:そうだね、『ファンクラブ』の時はポストロックのプロダクションを意識していたから。
-『ファンクラブ』は、『ソルファ』との違いというか方向性の違いを感じました。
後藤:あれは、ポストロックやニューウェーブのリズムセクションに対する考え方を導入したくて、ドラムにとにかくうるさく言ってたんです。
-それは後藤さんがみなさんに「こういうことをやりたい」って伝えるんですか?
後藤:そう、潔に「変わったことやって」って当時は言ってました。
-それを言われて、どうでした?
伊地知:しんどかったんですけど、引き出しを増やさなきゃなって(笑)。
後藤:潔にとっては『精神と時の部屋』だったんじゃない(笑)。でもそれですごいパワーアップしたと思いますよ、『ファンクラブ』はドラムのアルバムだと思うし。
伊地知:その後もしばらくは抜け出せてなかったから、8ビートはやってきてなかったんだけど。
後藤:そうだね、『ワールドワールドワールド』もその次の『未だ見ぬ明日に』も構成が複雑になっていて。1周回ってきた感じは確かにあるから、そういう意味では原点回帰と言われても仕方がない。
-意識はしていなかったけど、結果そうなっている部分があるっていう。
後藤:10周年を経て1周回った感じはあるから。自分たちはそんなつもりはなくてもはたから見たら原点回帰と言われるのかもね。いくらか上積みはあるはずなんだけど。
【interview後半】ASIAN KUNG-FU GENERATIONが語る、音が繋ぐ4人の関係性
『Easter』

『Wonder Future』