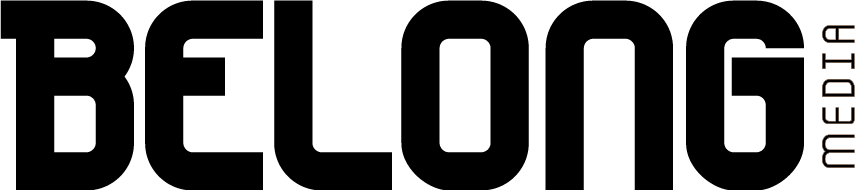最終更新: 2020年3月19日
80年代~90年代のUS、UKオルタナティヴのエキスを十分に吸収し、自分たちなりに解釈・提示してきたバンド、ザ・ノーベンバーズ。2010年にリリースされた彼らなりのオルタナティヴ・ロック絵巻というべき『Misstopia』が既にこのバンドの一つの完成形なのかと思ったが、ここ数作はそこから更に挑戦的な姿勢を見せている。方向性としては、『Fourth wall』で見せた攻撃的なゴシック・ロック路線を引き継ぐ作風に見えるが、そこにニューウェイヴ的な透明感が加味されているように見える。個人的には淡々としながらも楽曲をグイグイ引っ張っていくドラムが初期のThe Cureみたいで素晴らしい。フロントマンの小林祐介はバンドのロールモデルとしてL’Arc-en-Cielを挙げていたが、確かにラルクもゴスやニューウェイヴを日本人的に解釈しポップネスを得たバンドだったな、とふと思った。
終盤の「Ceremony」「Flower of life」はその透明感を押し出したドリーミーなパートで、近年のバンドで言うとTheRadio Dept.なんかを彷彿とさせるような、ひんやりとした寂寥感がある。そんなサウンドの上で歌われていることは、未来のために何を「選ぶ」かだ。《何になりたい?/どこへ行きたい?/誰といたい?/何が食べたい?/この街で選べるかな/この国で選べるかな》というリリックを初めとして、彼らは「何を選択するか」をリスナーに問いかける。これが正解だ、などとは突きつけたりはしない。だが、混沌を少し楽しんでいるように見える。《息が切れそう足はもつれそう/でも今日はまだ/遊び足りない/踊り足りない/そうだろ》。混迷を極めた社会情勢だけでなく、音楽シーンや音楽産業、音楽の聴かれ方の変化など、音楽家やリスナーの周りには深い泥沼のような混乱があると近年特に感じるが、彼らは、何を疑い何を信じるかを自分の手で選んでいけばいつか「これで良かったんだ」と思える瞬間があるはずで、それこそが「幸福」なんだよ、と投げかけている。そんな彼らの姿を僕は支持せずにはいられないし、時に痛々しいほどのノイズや叫びが聴こえるアルバムではあるものの、音楽への愛情やリスナーへの誠実さがにじみ出ている、ある意味暖かみのある一枚だと思う。