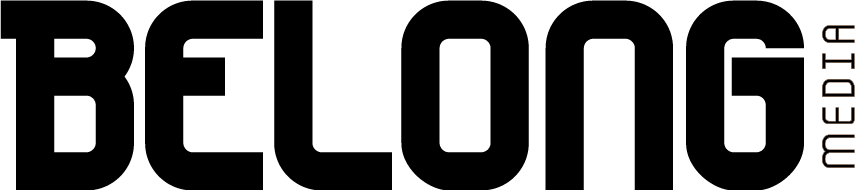最終更新: 2020年3月6日

今回の特集“YOUTHWAVE”では、物心のついた頃からインターネットへアクセスできる“デジタルネイティブ”の時代に生まれたアーティストを中心にインタビューを行った。
その中でもYkiki Beat(ワイキキビート)は「Forever」の映像が公開されるやいなや国内だけでなく、海外にも大きなインパクトを与えた。
彼らが証明したのは日本人でも海外と対等もしくはそれ以上の音楽を作る事ができるという事。
伝説のバンドBLANKEY JET CITYのベーシストである照井氏もYkiki Beatを評して、“日本のバンドとは思えないセンスを感じる。(中略)明らかにNew generationだと感じた。グラミー賞とか受賞する日本人アーテイストがこれから出てくるのかもしれないな。”と自身のブログに綴っている。
それではそのYkiki Beatは今、どんな事を考え、音楽を作っているのだろうか。メンバー全員に話を聞いた。
インタビュー前半はこちら
アーティスト:秋山 (Vo./ Gt.)、嘉本 (Gt./Vo.)、野末 (Syn./Vo.)、加地 (Ba./Vo.)、関口 (Dr.)インタビュアー:まりりん 撮影:Masahiro Arita
-レコーディングで印象に残っていることや大変だったことはありますか。
野末:アルバムを全曲レコーディングするのは初めてだったので、体験したことのない事ばかりでした。予定よりも遅れたし、時間もかかりました。みんな悩む事も多くて。
秋山:曲も昔からあるものをただレコーディングすればいいだけじゃなくて、新しく作り直したり、入れ替えたりする中で、アレンジできてないままレコーディングすることもたくさんあって。じゃあどうするっていうのをその場で考えないといけないこともあったし。あと「Forever」を録った時と別のスタジオだったので、音の鳴りやアンプも違うものだったりで、そこもまた新しく考え直さないといけない面がたくさんあって。音作りにしてもアレンジもその場で考えないといけないことがたくさんあって、延々と同じ1フレーズを一日中考えないといけない日もありました。逆にすんなりいくところは早かったりとかもあったんですけど、かなり難航した印象はありましたね。メンバー同士は関わり方が積極的になったかなと思います。前は全部自分で作って自分でアレンジして、これをやってくださいって感じだったので、みんなからしたらコピーしている感じに近かったのかもしれない。でも今回は出来上がってないまま作業に入ったから、メリットもデメリットもあったと思うけど、それぞれが自分のアイデアを持ってくる余地が生まれたんじゃないかなと思います。それぞれのメンバーの頭で創作することができるようになったかなって。バンド全体として、少しアクティブになれたかなと思います。
-自分たちで考えなきゃいけないということが求められてどうでしたか。
加地:今までだったら秋山がデモ作ってきた曲をみんなでライブで演奏するという形だったんですけど、自分が作ったフレーズがあってもライブで発表するだけだったので、自分が考えたのもが形に残るっていうのは嬉しいなと思いました。
-次号のBELONGは前回特集した“YOUTHWAVE”という内容をもう一度やろうと思います。“デジタルネイティブ”がインターネットを通じて、膨大な音楽のクラウドにアクセスし、新しい音楽を作り始めているって内容です。実際に邦楽・洋楽の垣根を越えるバンドが続々と現れていると思うのですが、世代的にYkiki Beatはデジタルネイティブだと思うのですが、どうでしょうか?
秋山:願わくばどこにも属したくないなっていうのがあって。今新しい東京のインディーシーンが熱いとか、このバンドとどこのバンドが新しいとか、色んな言い方がされていますけど、そのバンドたちとも俺れたちは絶対に違う考え方をしていて、違う感覚を持っていると思います。信頼できるバンドも信頼できる音楽もあるにはあるんですけど、その人たちとも違うと思うし。だからこれらのバンドとこの時代に生まれて必然だよねってとこに俺らはあんまりはまりたくないんですよ。確かにその恩恵は受けているのかもしれないですけど。デジタルなものが生まれて恩恵を受けた面もあるし、でもそれがなかったとしても自分にはできるところがたくさんあったと思うし。その時代だからできた、その時代だからできなかったっていうのは自分としては思っていないので。難しい質問ですけど、もしもは存在しないじゃないですか。もう過去に関しては事実しかないので。実際に自分たちはインターネット以降に生まれてるし。何とも言えないですけどインターネットがなかったとしても自分たちは良い音楽を作ってるべきだと思いますし、他の同じ世代の人たちと結託したいかって言われたら別にそういうところもないのが正直な所です。
-私もYkiki Beatは“YOUTHWAVE”の筆頭でありながらも、何か一線を画しているように感じていました。今の“YOUTHWAVE”のシーンの流れは今度どうなっていくと思いますか。
秋山:YOUTHWAVEの筆頭だとは僕たち自身思っていませんが、いつの時代も結局は本当に才能のある人しか残らないと思います。才能のある人は自分たちでやっていくじゃないですか。その流れみたいなので特集するとボロが出たり、嘘くささがあったりするので、そういうところとは距離を置き始めている人のほうが自分の頭で考えていると思いますし、そういう人たちのほうが残っていくと思います。今はなあなあでやってる人たちはお金の力で残っていくか、自分たちに無理がでてやめていくかのどっちかだと思います。
-その特集では、古い年代のアーティストでも自分が知らなければ、新しいという価値観があるようです。その考え方に共感する部分はありますか?
秋山:自分にとっては新しいというのはあるかもしれないですね。
野末:昔のアーティストは関係ない気がしますね。年代関係なしにしっかりメロディを持ってる音楽はいつの時代に聴いても新鮮に聴こえると思います。そういうのがいいなと思います。
秋山:新鮮に聴こえるというのはあると思いますよ。知らなかったものは全部新鮮なはずなので。例えばオアシスは知っていて自分の中で古かったとしても、ビートルズは知らなくて聴いてみると新鮮だと感じるかもしれないし。全く未知の音楽を聴くのとビートルズを聴くのとでは、自分の中で同じ新鮮という感覚でも別のタイプの新しいって響き方だと思うので。何を論じるかで変わってくるんですけど、知らないものが新鮮っていうのはいつの時代のアーティストであろうがアートであろうがあると思うので、それは今の人たちに限った話ではないと思います。少なくとも質のいい本物の音楽は古くならないと言いますよね。新しいとは別だけど今でも昔でも来年でも10年後でも聴ける音楽っていうのはいつの時代もあるかもしれない。

-Ykiki Beatの活動のスタイルに影響を与えたものはなんでしょうか。
秋山:日本のバンドと同じようにCDを出すというのは嫌だっていうのがみんなあって、『Forever』を7インチで出したみたいに、みんなの好きなバンドに近いスタンスでやろうと思ってます。
加地:簡単に言うとすれば、アメリカやイギリスのDIYでやってるバンドのようにやりたいですね。イベントの打ち方にしてもアナログとデジタルのリリースの方針にしても、向うの若い子たちは柔軟というか、新しいことにすごく貪欲だと感じていて。リリースのやり方や音楽だけじゃなくて、音楽活動のスタイルもインターネットで知る機会がたくさんあったので。あと音楽という意味では大学時代もそうでしたし、東京でかなり面倒を見てくれた人たちもインディーロックだけじゃなくてハードコア、ノイズ、もっとマニアなものから民族音楽など、色んなジャンルの音楽を聴く人がいて。音楽的な影響って意味では自分たちの周りに、自分たちとは違うタイプの音楽を聴く人たちがいたってことが大きいと思いますね。
-海外を見据えて活動していると思いますが、日本の音楽の強みと足りないものは何だと思いますか。
秋山:日本の音楽の強みはみんなストイックな所だと思います。真面目というか、良くも悪くもかもしれないんですけど、一度ハマったら掘る人たちが周りにたくさんいて。海外で会ったちょっとしたバンドマンよりも、圧倒的に広い範囲で音楽に詳しい人たちが、日本にはいると感じていて。その探求心というか、妥協せずに掘っていくタイプの人とか、技術的にも本当に練習してめっちゃうまい人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりクリエイティブな事や新しいことに挑戦する人が少ないかなと思っていて。もともとあるフレーズを自分でもやったりする事や、自分の手癖に安住して昨日弾いたフレーズを今日も弾くことしかできない人とかが多いなと感じていて。あと文脈をあんまり理解してない人が多いなと思います。50、60、70、80年代と流れがあってこの音楽があってこの影響を受けて、だから面白いっていう。言葉にしてもロックとは違うかもしれないけど、ジャンルとしても音楽としてどういう性質を持っているか、どういうところから来ているかっていう文脈ですね。あとは文学性。J-POPだと愛してるや会いたいっていう事を“愛してる”、“会いたい”としか書けない人がたくさんいると思うんですけど、それを詞にどう落とし込むかっていう実験なり創作なりをしてない人がたくさんいると思います。そういう意味では日本人って全員そうというわけではないですけど、傾向として文脈を理解していない人と文学性がない人がたくさんいすぎるかなと思うことが多いですね。
加地:最近ジム・オルークのライブを見たんですけど、バックバンドが全員日本人で、海外のバンドと違うなって。バイオリンの人がいたんですけど、弾き方がめちゃくちゃ叙情的で。
秋山:日本の音楽は湿気っぽいって感じるけど。悪い意味ではなくてね。そういうのが聴きたい時って日本の音楽しか聴けない時もあるし。
野末:強みとか弱みじゃないけどなんか違うってのはあるよね。
-音楽そのものだけでなくそれを取り巻く環境ではどうですか。
秋山:日本でいう中学や高校とかの年齢で、海外ではすごいバンドをやってる人がたくさんいるように感じましたね。The OrwellsやThe Districtsは18歳くらいでデビューして、世界で活躍していて。その子たちがその活躍ができたのは、そこで活動するリスクが少なかったからだと思っていて。日本でその歳でバンドを初めてもライブ1回するのに2万くらいは取られるとしたら4人バンドで1人5千円。そんなのはもうひと月に何回かやっただけで、中高生じゃとても賄えない。海外だったら、学校や教会で演奏したり、パブで演奏するってなってもタダでやらせてもらえたり、カジノでやってる人もいるっていうし。とにかく演奏できる機会がたくさんあって。選択肢がたくさんあるので、自分たちが演奏する機会があって、自分の家のガレージで練習できたり。練習するのにも日本はお金がかかるので。バンドとして適切な音量で演奏する機会が学生だと、本当に取りづらいと思うんですよ。その時期が自分たちの方向を決定づける重要な時期なのに。そういう意味では日本では活動するときに弊害があると以前から感じていたっていうのはあります。その他でいうと先月DYGLでアメリカに行ったときには、その手のバンドが好きな人たちにはすごく人気のあるようなバンドが3つくらい出るイベントで、入場料が5ドルくらいのものがざらにあって。こっちだとアマチュアの学生バンドが出るようなイベントでも2500円はかかる。見る機会って意味でも海外はかなり開かれているけど、日本ではお金がかかるから見にも行けない。だから本当にいいものも見れないし、自分たちがどうしたらいいかも分らないまま就職しようってなる流れは当たり前かなって思うので。バンドに限らないことなんですけど、創作活動って自由に自分がやりたいと思った時にやるように表現する、練習する環境が日本にはあんまりないんじゃないかなっていうふうに思ってます。この二つはかなり昔から感じていました。
-Ykiki Beatは今後どこを目指して活動していくのでしょうか。
秋山:1枚アルバムを出すという目標は達成したので、これからツアーにも行きたいと思っていて。それが一通り終わったら、学生時代から計画していた海外に拠点を移して、むこうで生活しながら活動するというプランを具体的に練っていて。もともとはDYGLだけで行く予定だったんですけど、こういう状況なのでDYGLに合わせてYkiki Beatも移ろうとしていて。その先にどこに到達したいかっていうの目標は、まだ自分たちの中にはないんですが、海外に行っていい影響を受けながら自分たちの納得できる作品を作ることが大きな目標かなと思っています。海外の影響を受けて自分たちの出したい音を研究して、次の作品に生かすっていうのはかなり近い目標かもしれないですけど、それができないと次のステージにすら行けないと思うので。
-今回のアルバムをどんな人に聴いて欲しいと思いますか?
秋山:みんな聴いてくれたら嬉しいですけどね。自分も学生時代にこういう活動をやってる人が周りにほとんどいなくて。ギリギリここまで繋いで来られましたけど、どっかでもういいやってなったりしそうな時もあったんですよ。音楽がギリギリ繋いでくれて、良い音楽を聴いたり、そういうものを教えてくれたり、共有してくれたり、バンドやってくれる人がいたからいいけど、それがなかったらそもそも自分が本当に好きな音楽なりアートなりのテイストを知らないままだったのかなと。本当はすごい作品を作れるのにそれを知らないまま過ごしている人がたくさんいると感じていて、特にこれからの子たちの中でそれに気づいていない人がいたら、この作品を聴いてYkiki Beatの先にあるものも聴いて、自分の好きなテイストに気づいてくれたらいいなと思います。本当は全員聴いてくれたら嬉しいですね。
-最後に伝えたいことなどはありますか。
野末:最後は関口先輩にまとめてもらおうか。
秋山:彼だけちょっと年上なので、こういうときはやっぱり関口先輩に。
関口:こういう時だけ持ち上げる(笑)。まぁ中身がすべてなんじゃないでしょうか。いいものを作ればいいんじゃないかなってことですよね、秋山さん。
加地:日々勉強ですってことですか?
関口:それだ。
野末:加地が言ったことじゃねーか(笑)。
関口:常に前進しているような雰囲気がバンド内にあるので、レコーディングしていた時よりも日々日々変わっているようないい流れがあると思います。そういうところで自分たちの納得のいくものが作れたらいいですね。日々勉強です(笑)。
インタビュー前半はこちら