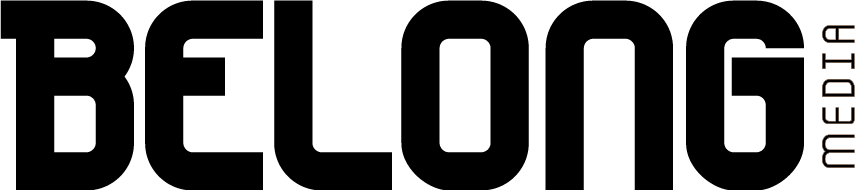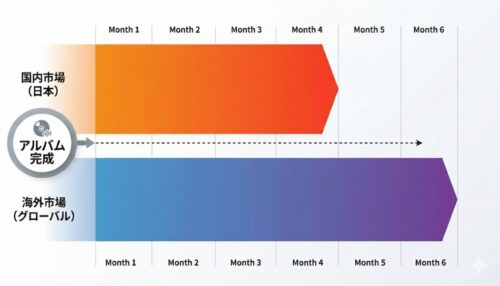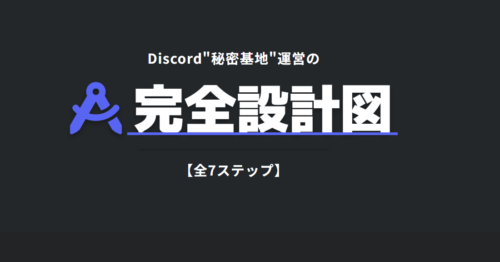最終更新: 2025年2月18日
“プロインディー”という言葉はもう覚えて頂けただろうか?
この言葉は筆者の造語で、レーベルに所属せず、自主レーベルで音楽活動を行いながらも、プロとして成功を収めるアーティストを指す。
近年、デジタル配信やSNSの普及により、インディーアーティストが自らの力でファンを獲得し、音楽業界で活躍するチャンスが広がっている。
しかし、その一方で、SNSの効果的な活用方法に悩むアーティストも少なくない。
SNSは、楽曲の告知やファンとの交流だけでなく、新たなファンの獲得や業界関係者とのつながりを生む重要なツールだ。
しかし、“どのようにSNSを活用すればよいのか”“時間をどのように割り当てるべきか”など、多くの疑問が浮かぶことだろう。
今回も、メジャーレーベルで新人発掘を担当していた経験を持つまりりんに話を聞いた。
その現場で培った経験から、“プロインディー”を目指す新人アーティストが効果的にSNSを活用するためのヒントを提供していく。
まりりんは、新人アーティストの発掘においてSNSを積極的に活用しており、その視点からアドバイスを聞いてみた。
この記事では、“プロインディー”を目指すあなたがSNSをどのように活用すべきか、その具体的な方法と考え方を深掘りしていく。
※この記事は、一部有料となっており、記事途中まで無料で読むことができる。
テキスト:Tomohiro Yabe、まりりん 使用ツール:Gemini、genspark 編集:Tomohiro Yabe
新人バンドからの質問

本コラムを定期購読いただいている新人バンドから、前回に引き続き、以下のような質問が寄せられた。
“インディーアーティストのあるべきSNS運用方法を教えていただきたいです。(どうすればリスナーやレーベルの人に見つけてもらいやすいでしょうか?フォロワー数はどれほど重要な指標なのでしょうか?)”
今回はアーティストのSNS運用方法について、まりりんの経験を基に、その秘訣について教えてもらう。
アーティストのSNS活用での悩み

インディーアーティストがSNSを活用する上で、よくある悩みについて、ネット上の内容をもとにリサーチを行った。
まず運用初期においてはSNSに何を投稿すればよいか分からないということが挙げられる。
これについては、活動が本格的になるにつれて、ライブや楽曲の告知などで徐々に投稿する内容に悩まなくなってくるだろう。
一方で、根源的な悩みになっているのは運用が本格的になってくる段階では時間不足が挙げられる。
本格的にやろうと思うと、一般的に週10時間程度は必要とされるSNS運用は、本来、最も重要な楽曲制作との両立が困難になる。
例えば、Instagramのリールひとつとっても、2~3日もの時間を要し、作曲活動が停滞してしまうケースも。
次に、継続的な発信を自身に課すことで、負担が重くのしかかっている。
単なる告知だけでなく日常的な発信が求められる中、例えば週3回のオリジナル動画作成を課すなど、続けることに精神的な疲れを感じるアーティストが多く存在するようだ。
これらの問題の根底には、アートとマーケティングの両立という根本的な葛藤が存在する。
楽曲のクオリティよりもSNSの見た目が重視される現状に違和感を覚えながらも、デジタル時代への適応を迫られているのが現代のインディーアーティストの実情と言えるだろう。
そもそも上記で紹介したように、週10時間程度をかけ、本格的にSNSを運用をする必要があるのだろうか?
また、メジャーレーベルや新人発掘の担当者はアーティストのSNSのどのような部分をチェックしているのか?
それらの疑問や効果的なSNSの活用方法について、まりりんに話を聞いた。
この記事を単体で購入する場合はわずか200円。さらにお得な月額サブスクリプションはたったの500円で、すべての記事をいつでも好きなだけ読んでもらえる。
サブスクは今なら3日間の無料お試し付き。この機会にぜひ続きを読んで、もっと深く“プロインディー”の世界について知ってほしい。
この企画を始めて一ヶ月経ったが、記事単体と月額のサブスクを併せて、12回購入されているので、ぜひとも参考にしてほしい。
また、一ヶ月500円の月額サブスクリプションに入ってくれた方については、メジャーレーベルもしくは音楽業界で気になることがあれば、今回のように記事内で回答させてもらう。
この機会に加入していただき、知られざる音楽ビジネスの裏側について知っていただきたい。
それでは本題に入っていこう。
これまでのプロインディーの記事について