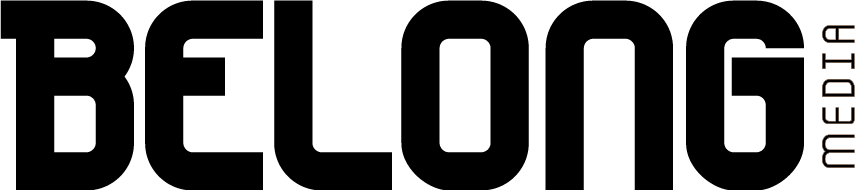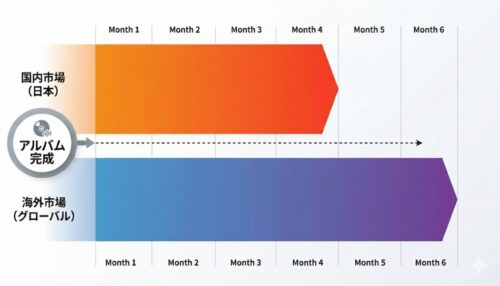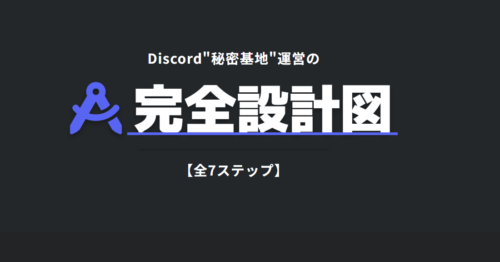最終更新: 2025年3月31日
足立美術館の日本庭園:“育てる”哲学の具現化
島根県安来市に位置する足立美術館は、横山大観らの近代日本画コレクションで知られるだけでなく、その日本庭園の美しさでも世界的に評価されている。
米国の日本庭園専門誌『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』のランキングで22年連続日本一に選出されているこの庭園は、創設者・足立全康“庭園もまた一幅の絵画である”という信念のもとに作られた。
また、足立美術館は基本的に毎日開館しており、庭師たちが毎日開館前に庭園を掃除し、徹底的な維持・管理を行っているのも見逃せないポイントだ。
借景の芸術:自然との対話

足立美術館の庭園の最大の特徴は“借景”の巧みな活用だ。
借景とは、庭園の外にある山や森などの自然景観を庭園の一部として取り込む日本庭園特有の手法である。
この借景の概念は、庭園デザインにおける“育てる”哲学の核心を示している。
庭師は自然をコントロールするのではなく、自然と対話し、その力を引き出す役割を担う。
これはブライアン・イーノがジェネレーティブ音楽で示した、作曲家がシステムに一定の自律性を与え、音楽が自ら展開していくことを許容するアプローチと驚くほど共鳴している。
“音の庭園術”:ジェネレーティブ音楽と日本庭園の融合

ブライアン・イーノのジェネレーティブ音楽と足立美術館の日本庭園。
一見すると全く異なる領域に思えるこの二つの芸術形式だが、その根底には“育てる”という共通の哲学が流れている。
ここでは、この二つの創造的アプローチの融合点を探り、“音の庭園術”という新たな創作の可能性を提案したい。
両者に共通するのは、クリエイターが全てをコントロールするのではなく、自然な成長や変化を許容し、導くという姿勢だ。
イーノは自身のアプローチを説明する際、音楽を川にたとえている。遠目でみれば静止画のように見えるが、川の水面は絶えず変化している。
これは足立美術館の庭園における時間と変化の考え方と響き合う。
庭園は一見すると静的な芸術に思えるが、季節や天候、時間帯によって絶えず変化し、同じ景色は二度と見られない。
また、両者とも“フレーミング”の考え方を重視している。
足立美術館の“生の額絵”や“生の掛軸”は、自然の一部を切り取り、芸術として提示する。
同様に、イーノのジェネレーティブ音楽も、無限の可能性の中から特定のパラメーターを設定することで、音楽的な“フレーム”を作り出している。
さらに、両者に共通するのが“間(ま)”を大切にしているということだ。
日本庭園では空間的な“間”が重要な役割を果たし、石と石の間、木と木の間の空白が庭園の表情となる。
イーノの音楽でも、音と音の間の空白、沈黙が重要な要素となっている。
インディーバンドのための“音の庭園術”実践法

では、ブライアン・イーノと日本庭園に共通する、“作る”から“育てる”という考え方を取り入れた“音の庭園術”を実践するにはどうしたらいいのだろうか?
ここからは、“音の庭園術”を実践するヒントとして、私たちが10年を超え、継続して取材しているThe Novembersを例に出して説明していきたい。
取材を進める中で、彼らは10年間自分たちのアレンジや演奏方法を見直し、常により良い、いやよりかっこいい音楽を目指してきた。
それは“作る”から“育てる”という考えがバンドに根付いており、日本庭園のように日々手入れを欠かさずに行ってきた結果である。
この記事を単体で購入する場合はわずか200円。さらにお得な月額サブスクリプションはたったの500円で、すべての記事をいつでも好きなだけ読んでもらえる。
サブスクは今なら3日間の無料お試し付き。この機会にぜひ続きを読んで、もっと深くプロインディーの世界について知ってほしい。
この企画を始めて、毎週更新しながら4ヶ月が経ったが、記事単体と月額のサブスクを併せて、20回以上購入されているので、ぜひとも参考にしてほしい。
この機会に加入していただき、“編集”から生まれるオリジナリティの秘密について知っていただきたい。
これまでのプロインディーの記事について