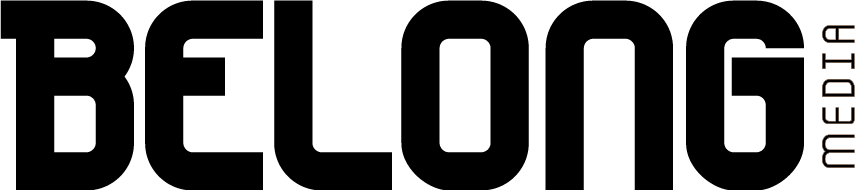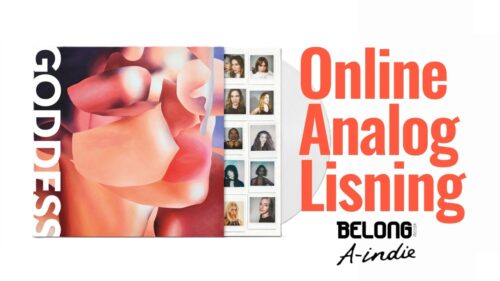最終更新: 2025年7月7日
全2回にわたり、日本初となる“オンラインアナログ試聴会”の企画立案からリハーサル、そして海外レーベルとの協業が実現するまでの舞台裏を追いかけてきた。
技術的な試行錯誤と、国境を越えた交渉の末、私たちの挑戦はついに2025年6月7日、本番当日を迎えた。
かっこよく書いてはみたものの、実情は多くの失敗かつバタバタの運営により、会場である喫茶店でアイスコーヒーで一息つく暇もないほどであった・・・。
果たして、アナログレコードの”空気感”をオンラインで届けるという試みは成功したのか。リスナーはどんな反応を示したのか。
そしてこの経験は、プロを目指すインディーバンドにとって、参考になることとは何か。
最終回となる今回は、イベント当日の実況レポートから、集客、参加者の反応までを赤裸々に検証し、この前代未聞の実験がインディーシーンに残したものを総括する。
海外の成功事例から見る“リスニングパーティー”の価値
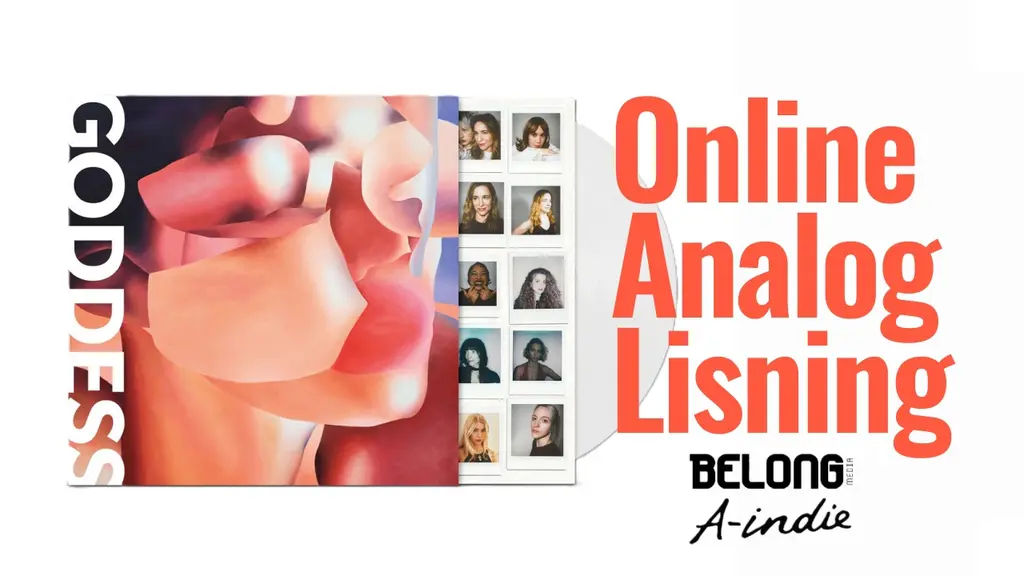
テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、Gemini 編集:Tomohiro Yabe
本題に入る前に、改めて海外の類似イベントの成功事例を見てみよう。
前述の“Tim’s Twitter Listening Party”は、コロナ禍において孤立しがちだった音楽ファンに、巨大な”共体験”の場を提供した。
ファンはリアルタイムで感想を共有し、アーティスト本人から制作秘話が明かされることもあった。
これにより、アルバムという作品への理解が深まり、アーティストとファンの絆はより強固なものになった。
また、Phoebe BridgersやSufjan Stevensといったアーティストは、新作リリース時にYouTubeでプレミア公開を行い、ファンがチャットで期待や興奮を分かち合う、一種のオンライン上の”フェス”空間を創出してきた。
これらの成功事例に共通するのは、単に音楽を聴かせるだけでなく、“同じ瞬間に、同じ体験を共有している”という感覚を提供している点である。
この一体感こそが、デジタル時代における音楽プロモーションの新たな付加価値となっている。
私たちの挑戦も、この”コミュニティ体験”を、アナログレコードというメディアを通じて実現することを目指したものであった。
体験の”質”を問い直す

私たちの試みは、音楽の届け方における“体験の質”を問い直すものでもある。
効率や手軽さが重視されるストリーミング時代において、あえて手間のかかるアナログレコードを、特別な環境で聴く。
この”非効率”な行為にこそ、音楽と深く向き合う豊かな時間がある。
このイベントが成功すれば、インディーシーンにおいても“ただ配信する”だけではない、多様なプロモーション手法の可能性が広がるはずである。
小規模なカフェやレコードショップと組んだオンライン試聴会、アーティスト自身がこだわりのオーディオ環境から配信するイベントなど、アイデアは無限に考えられる。
私たちの挑戦は、その第一歩となるはずであった。しかし、現実は計画通りには進まない。ここからは、その生々しい記録である。
ここから先は有料記事となる。
有料部分では、イベント当日に起こった想定外の事態、苦戦した集客のリアルな数字、そしてZoomと急遽始めたインスタライブの同時配信というドタバタ劇の全貌を、ミーティングの議事録を基に再現する。
成功も失敗も包み隠さず語ることで、次に続く挑戦者のための、実践的な”教訓”を残したいと思う。この挑戦の結末を、ぜひ最後まで見届けて欲しい。
この記事を単体で購入する場合はわずか200円。さらにお得な月額サブスクリプションはたったの500円で、すべての記事をいつでも好きなだけ読んでもらえる。
サブスクは今なら3日間の無料お試し付き。この機会にぜひ続きを読んで、もっと深くプロインディーの世界について知ってほしい。