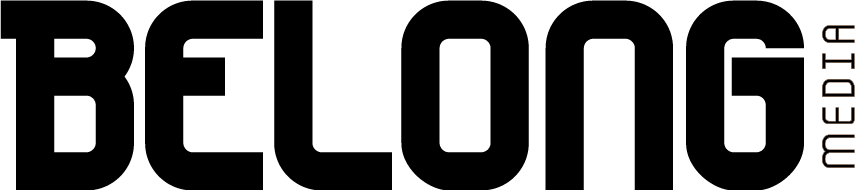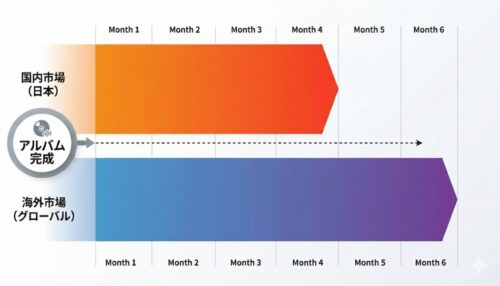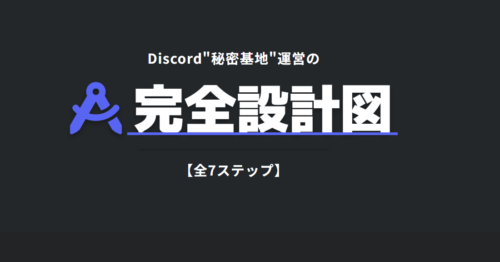最終更新: 2025年7月12日
先日、日本のバンド・メコンのインタビュー記事を編集していて、思わず手が止まった。
自分たちの音楽を語る中で、彼らはこう言っていた。
まずはアメリカですね。WeezerやBig Thiefが大好きなので。(中略)どちらかというとアメリカの方が受け入れられそうだな、と。
この言葉が、ずっと頭の片隅にあったモヤモヤとした疑問に、一つの輪郭を与えてくれた気がした。
これまで海外の音楽を聴いてきたリスナーは、アメリカのロックとヨーロッパ、特にイギリスのロックの間に”なんとなく”存在する質感の違いを、肌で感じ取ってきたはずだ。
この感覚、あなたも覚えがないだろうか?
メコンのインタビューから

テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、Manus、Gemini 校正・編集:Tomohiro Yabe
例えば、メコンのインタビューにも何度も出てきたRed Hot Chili Peppers(以下レッチリ)を聴けば、理屈抜きで身体が動き出すように。
太陽が照りつけるカリフォルニアの乾いた空気みたいな、開放的で”肉体的なファンクネス”。
一方、Radioheadの音楽を聴くと、どこか内省的で、緻密に組み上げられた建築物の中を彷徨うような感覚に陥る。
霧深いイギリスの古城を思わせる、”内省的で構築的な美しさ”のことだ。
同じ”ロック”なのに、なぜこんなにも違うのか?それは彼らのキャラクターの違いなんだろうか?
この問いは、私を含めてきっと多くの音楽ファンやバンドマンが、言葉にできずに抱えてきたものではないか。
メコンの言葉は、その違いが単なる好みやスタイルの問題ではなく、もっと根深い文化的土壌の違いに根差している可能性を示唆していた。
そして、最近観た映画『教皇選挙』の記憶が蘇る。バチカンを舞台にしたその映画で描かれていた、ローマ教皇選挙をめぐる荘厳で儀式的なカトリックの世界観。
もしかしたら、このパズルのピースは、キリスト教(カトリックとプロテスタント)という、あまりにも巨大な文化の中にあるのかもしれない。
これは決して宗教の優劣を論じるものではない。特定の信仰を推奨したり、ましてや批判したりする意図は毛頭ない。
あくまで、私たちが愛する音楽という表現を形作る一つの重要な”パーツ”として、キリスト教文化がどう作用してきたのか。そのルーツを探るというものだ。
この探求が、あなたが普段聴いている音楽に、新たな視点と物語をもたらすきっかけになることを願っている。
また、プロインディーを目指す皆さんにとっては、自分たちの音楽がアメリカとヨーロッパのどちらに受け入れられるのか一つの手がかりになればと思う。
ここから先は有料記事となる。
有料部分では、アメリカとヨーロッパの音楽の違いのルーツにあたる歴史的・文化的背景の深層に迫る。
レッチリの衝動とRadioheadの思索が、なぜ生まれたのか。
この記事を単体で購入する場合はわずか200円。さらにお得な月額サブスクリプションはたったの500円で、すべての記事をいつでも好きなだけ読んでもらえる。
サブスクは今なら3日間の無料お試し付き。この機会にぜひ続きを読んで欲しい。
あなたの音楽ライブラリが、まったく違って聴こえることになるかもしれない、決定的なヒントがここに。