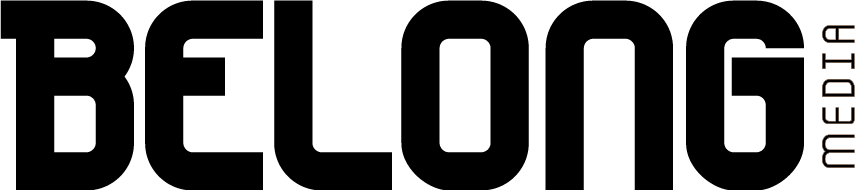最終更新: 2025年11月10日
BELONG Media / A-indie編集長のyaboriです。同じ音楽を聴いても、人それぞれ感じ方は違うもの。
ましてや育った国や文化が違えば、その違いはもっと面白くなる。
今回お届けするのは、国境を越えた特別な“音楽のクロスレビュー”企画!
執筆者は、数年ぶりにレビューを書くことになった滝田くん(Yuuki Takita)と、遠くアルゼンチンに住みながら日本文化を愛するRAM。
Discordでの偶然の出会いをきっかけに、前回はアメリカの新人バンド、Racing Mount Pleasantのアルバムを聴き、それぞれの視点から感想を語り合ってもらった。
そして今回は、オーストラリアのDJ兼音楽プロデューサーNinajirachi(ニーナジラーチ)のデビューアルバム『I Love My Computer』を深掘りしていく。
地球の裏側で生まれた二つのレビューがどんな“化学反応”を起こすのか、ぜひ楽しんで欲しい。
The English cross-review for Ninajirachi『I Love My Computer』 is here.
Ninajirachi『I Love My Computer』クロスレビュー

レビュアー:RAM、滝田優樹(Yuuki Takita) 編集:yabori(Tomohiro Yabe)
RAMの視点から
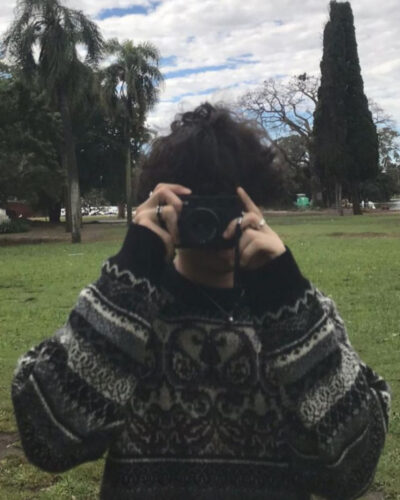
再び、滝田さんとのクロスレビューを執筆する機会に恵まれた。
彼はBELONG/A-Indieに欠かせない書き手であり、その筆力と珠玉のインタビューの数々に、深い尊敬の念を抱いている。
クロスレビューの魔法は、同じ一つのアート作品に向けられた、書き手それぞれの視点が織りなすコントラストにあると信じている。
今回、私たちが語り合うのはNinajirachiのアルバム『I Love my Computer』。
私にとって個人的に深く心に響いた最新リリース作品だ。
滝田さんがこの作品をどう受け止め、どう解釈したのか、そして私らの見解がどんなコントラストを描き出すのか、好奇心は尽きない。
“指と、目と、マウスと、スクリーンがあれば、何だってできる”
Ninajirachiとは

Ninajirachiは、2017年から活動するオーストラリアのDJ兼音楽プロデューサーだ。
彼女の音楽的背景は、10代の頃にFL Studioを独学で習得したことから始まる。
その後、数々のシングルやEPをリリースして経験を積み、その集大成として、今年初めにデビューアルバム『I Love my Computer』を発表した。
このジャケットアートを一目見れば、リスナーは彼女が今作に込めた大胆な意図を掴み取ることができるだろう。
そこには、今世紀の最初の四半期にインターネットと共に成長した子供たちのカルチャーを構成した、ありとあらゆる視点の上に横たわるNinajirachi自身の姿がある。
その大胆さは、オープニングのトラック群でさらに加速する。
「London Song」は、分厚いシンセの質感と催眠的なリズムで空中の沈黙を切り裂き、彼女のボーカルと感傷と相まって、コンピューター画面の青い光で彩られた非現実的な光景を描き出す。
続くトラック群は、この幻想の中で提示されたディテールをさらに深め、その世界観を強調していく。
「iPod touch」は、過ぎ去った瞬間への憧憬というよりは、むしろそれを祝福するかのように、2010年代初頭へのノスタルジックな追憶を見事に蘇らせる。
そして「Fuck my computer」は、これ以上ないほどの自信と誠実さをもって届けられる、一つのステートメントとして響く。
“I wanna f*ck my computer, ‘cause no one in the world knows me better”(私のコンピューターを抱きたい、だって、世界中の誰より私を分かってくれるから)。
“こんなに心地良いものを、どうして拒む必要があるの?”
アルバムが進むにつれて、私たちはインターネットと共に成長した人生の、共感に満ちた景色を目の当たりにする。
気になる相手の気を惹くために使えるツールを駆使した経験から、意図せずネット上で何かを見つけてしまい、心に傷を負った記憶まで。
中でも「Sing good」は、私にとってのハイライトだ。ほとんど童謡のようなメロディに乗せて、Ninajirachiは彼女がどのように音楽を書き始めたのか、その物語を語る。
あらゆる創造的なプロセスに付きまとう疑念、懸念、そして空想が、わずか2分半のトラックに巧みに集約されている。
しかし彼女は決してそれに屈しない。サビが来るたびに、こう言って疑念を振り払うのだ。
“I can’t really sing good, but I’m still gonna try it”(歌は上手くない、でも、やってみるんだ)。
“それはまるで、私と私のコンピューターが夜更かししている音みたい”
ミレニアムの変わり目に生まれ、このアルバムで描かれていることと非常によく似た経験のある私にとって、この作品はとりわけ特別なものに感じられる。
かつて、そんな長い夜があった。
疲れた目をコンピューターの画面に釘付けにしていた夜のことだ。
そこでは、その機械は夢見ることのできるすべてへの入り口であるだけでなく、誠実な親友でもあった。
外の世界がどうにも理解できなかった時、唯一すがりつくことのできたパートナー。
他のどんな時代であったなら、決して花開くことのなかったであろう、無数の友情や興味の世界へと導いてくれた存在。
この経験が、アルゼンチンでも、オーストラリアでも、日本でも、世界のどこであっても共有されているのだと知るたびに、いつも温かい何かが胸に込み上げてくる。
デビューアルバムで、Ninajirachiは、今やそのほとんどが記憶の中や、消えゆくデジタル空間にしか存在しないカルチャーを肯定する作品を創り上げた。
そして、そうすることで、彼女自身がこのカルチャーの象徴となったのだ。
彼女のアルバムのジャケットアートに描かれた、無数のケーブル、キーボード、スクリーン、そしてポスターと、全く同じように。
次のページこちら ⏩️