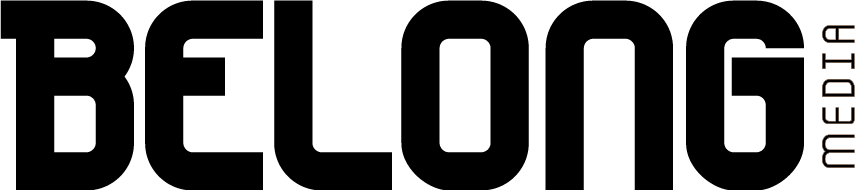最終更新: 2025年12月17日
音楽には国境がない。だからこそ、同じアルバムを異なる文化で育った人が聴いたとき、そこに生まれる視点の違いが興味深い。
今回はロキソニ(rockin’on sonic)での来日も決定した、アイルランドのJust Mustard(ジャスト・マスタード)が放つ最新作『WE WERЕ JUST HERE』。
そんな本作をアルゼンチン在住で日本文化を愛するRAMと、日本で音楽ライターとして活動する滝田優樹が徹底レビューを行う。
シューゲイズとエレクトロニカを慎重に融合したこのアルバムは、一度の試聴で聴き手の心を奪う力を持っている。
クリスタルのように透明感あるボーカル、ノイズに包まれたシンフォニー、そしてそれぞれのライターが思い浮かべたルーツについて。
二人のライターが辿り着いた共通点とは?国境を越えたクロスレビュー企画第4弾、今ここに公開。
また、後日私たちが行ったJust Mustardのインタビューも後日公開を予定している。
English article here 🔗
English
Just Mustard『WE WERE JUST HERE』クロスレビュー
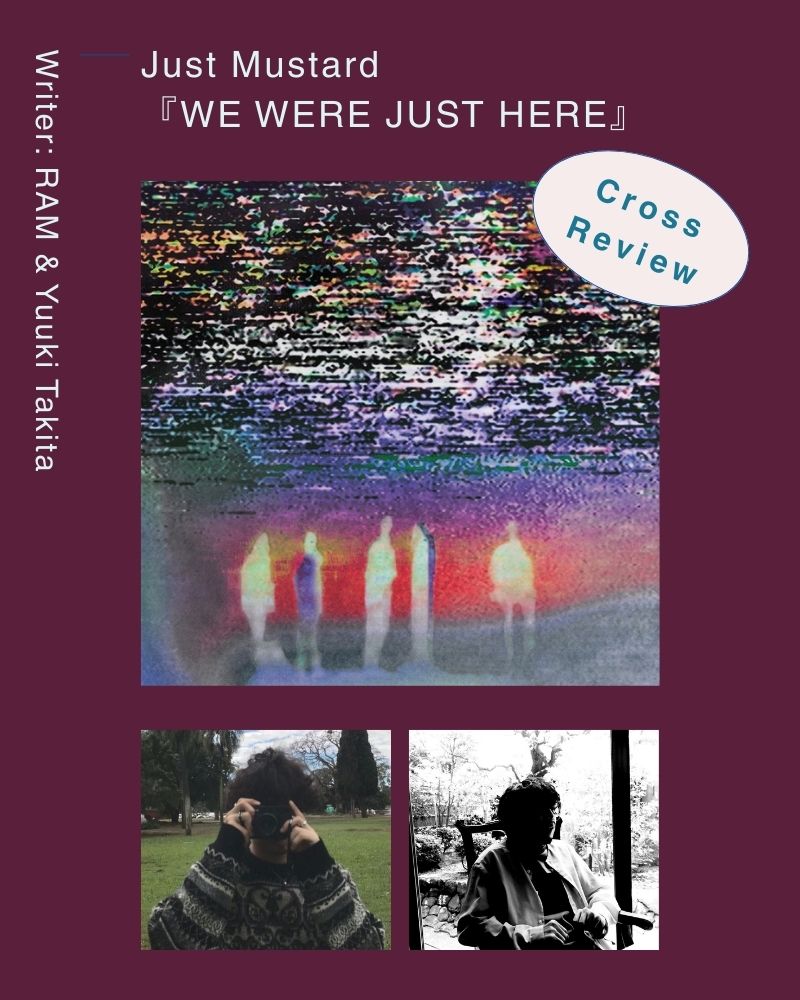
レビュアー:RAM、滝田優樹(Yuuki Takita) 編集:yabori(Tomohiro Yabe)
RAMの視点から

滝田さんと共に執筆を続けているこのクロスレビュー連載も、時が満ち、今回で第4弾を迎えることとなった。
今回、滝田さんから提案があったのは、アイルランド出身のバンド、Just Mustard(ジャスト・マスタード)による最新作『WE WERE JUST HERE』について書くことだった。
正直なところ、この企画が始まるまで、このグループの存在を知らなかった。
だが、彼らが提示する音楽に完全に心を奪われるまで、たった一度の試聴さえあれば十分だった。
エレクトロニック、シューゲイズ、ダンス、そしてインダストリアル・ミュージック

『WE WERE JUST HERE』で提示される10の楽曲は、抽象的で夢幻的なサウンドスケープの中に存在している。
その音像は、多岐にわたるジャンルの影響を織り交ぜて巧みに構築されたものだ。
エレクトロニック、シューゲイズ、ダンス、そしてインダストリアル・ミュージック……
このアルバムの随所に、そうした要素との親和性を容易に感じ取ることができる。
本来、あまりにかけ離れた影響元同士というのは衝突してしまいがちなものだ。
しかし本作において、バンドはそれらを極めて慎重に融合させている。
単に共存させるだけでなく、互いが互いを引き立て合うように昇華させているのだ。
アルバム全体としての完成度は極めて高く、その楽曲の流れはあまりにも自然である。
クリスタルのような透明感を持つボーカル

アルバムを通して、ボーカルは楽器の一部として溶け込むように、少し引いた位置でその役割を果たしている。
リードをとるケイティ・ボールの歌声は、明るく、クリスタルのような透明感を持ち、作品全体の夢見心地な感覚をより一層強固なものにしている。
時折、デヴィッド・ヌーナンの低音がそこに重なり、ケイティの声と呼応することで、二人の間には幻想的なデュオが生み出される。
不安やノスタルジー、そして移ろいゆく時の流れ
『WE WERE JUST HERE』が抽象的に語りかけるのは、不安やノスタルジー、そして移ろいゆく時の流れといったテーマについてだ。
作中に登場する自然界の情景描写も見過ごすことはできない。
それはまるで、鳥のように国境のない世界を俯瞰し、答えのない問を求めて彷徨う精神の流れを目で追うかのようだ。
青々とした草木、花々、そして空。
それらは私たちの理解を超越した時間と自然の摂理を知覚しているかのようで、幾多の生命を自由に流れゆき、学び、傷つき、癒やし、そしてまた挑むための時間を与えてくれる。
それは、傷ついた心を抱えた誰にとっても、完璧な処方箋となるだろう。
My Bloody Valentine、Aphex Twin、そしてGilla Band
『WE WERE JUST HERE』を聴いている間、私の脳裏には幾つかのアーティストの姿が浮かび続けていた。
いくつか名を挙げるなら、My Bloody Valentine、Aphex Twin、そしてGilla Bandだ。
嬉しかったのは、Just Mustardもまたアイルランド出身であり、実際にこれらのミュージシャンから影響を受けていると知ったことだ。
時代を問わず、アイルランドという土地は常に偉大なバンドを輩出し続けているようだ。
『WE WERE JUST HERE』によって、Just Mustardは、アイルランドの音楽シーンが今どこにあるのかという問いに対し、誇らしげにその手を挙げて応えてくれた。
アイルランドの偉大なアーティストたちの系譜に、その存在感を示したのである。
次のページこちら ⏩️