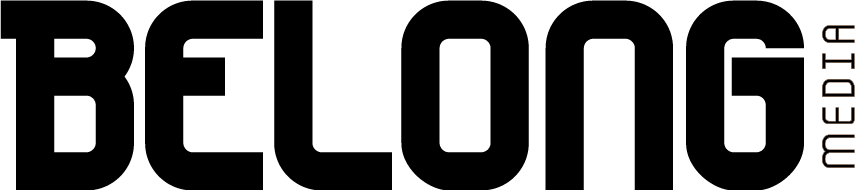最終更新: 2021年3月4日
今作『St.Vincent』の話をする前に、少しだけ寄り道をしたいと思う。
St.Vincent(セイント・ヴィンセント)ことアニー・クラークが、80’sのUSポストパンク最重要バンドのTalking HeadsのリーダーであるDavid Byrneとの共作『Love This Giant』を生み出したのは、2012年のことだった。
2013年を通過したいまになってみれば、その視座は、Arcade FireとDaft Punkの新作に見える<アフロ・ミュージックへの回帰ないしは接近>という姿勢と非常に近しい。
これまで培ってきた自らのサウンドに、Davidの白人流ファンク解釈に基づいたファンキーなホーンセクションを接続し、それがブラック・ミュージックを視野に入れたUSインディー・ミュージックの在り方を掘り下げた、
『Love This Giant』製作時の彼女は無意識のうちにそんなことしでかしたのだ、こんなことを僕は思っていた。彼女のポップ・ミュージックの先見性を見出す知性のようなものに惚れ込んだのは、言うまでもない。
翻って、自らの名前を記した今作『St.Vincent』はどうだろう。本作を一聴すれば、先程の指摘がただの偶然の一致であり、脇道に逸れて生み出されたものであったのだと気付かされる。
ありがちなスムースさを嫌いつつもメリハリある演奏を基調とする彼女の大黒柱は、一切変わっていない、むしろ共作を経たことで、本作はその大黒柱には一段と磨きがかかっている。
ガシガシと蹴り上げるようなリズムトラック、80年代のようなチープめいた音を奏でるシンセサイザー、多種に渡るホーン・セクションやギターサウンド、それらがコロコロと音色が変えいく。
クリーンな音色と歪んだ音色、エコーサウンドによる奥行きあるサウンドの広がり、いくつもの楽器に繋がるエフェクターが、チカチカと点灯を繰り返し、サウンドに変色と変様を促していく。
何よりも驚くべきは、これまでよりも少々カオス気味に走ったこの音の数々が、彼女の歌声とともにキレイにバランスを取ってサウンドを組み立てると、彼女のディスコグラフィの中で最もエレガントに輝く一枚になったのだから、脱帽モノだ。
2011年にリリースしたサード・アルバム『Strange Mercy』から2年以上もの間、文字通り息つく休む間もなくツアーとレコーディングを繰り返してきた彼女。
「葬式でもかけられるパーティ・レコードを作りたかったの」とは本人の言葉だが、悪ふざけにしか聞こえない行ないをコンセプトを掲げて、大まじめに取り組み、本作を生み出す。
アフロのようにちぢれた黒髪を白く染め上げて、ステージを優雅に歩きながらピンマイクで歌う、そんな彼女の姿を目に浮かべてみる。
どこか滑稽でバカバカしくも見えるが、彼女は今のところ、他者の視線には目もくれず、自己の美意識に従って音楽に夢中になっている真っ最中なのだと僕は思うのだ。
自身から滲む音楽への情熱と遊び心が渾然一体となった今の彼女、真なる<インディー・ミュージシャン>とやらが本作にいるのだと、強く念を<推して>おきたい。