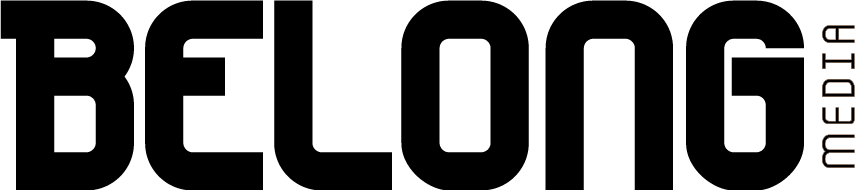最終更新: 2020年5月16日

Fanfarlo、ロンドンで結成された5人組男女混成のインディーバンドで、2006年にスウェーデン出身ミュージシャンのSimon Balthazarにより結成された。現在まで『Reservoir』(2009年)『Rooms Filled With Light』(2012年)と2枚のアルバムをリリース、本作『LET’S GO EXTINCT』は3作目となる一作だ。
Arcade FireやBeirutなどと比較され、早耳なインディー・ミュージックファンの間でここ数年知名度があがっている「オーケストラル・ポップ」や「チェンバー・ポップ」といったタグがつけられた彼ら。
もちろん、インターネットを使えば、いくらでも彼らのような傾向を持った名のあるバンドやSSWが見つかる。だが、彼らの大半がイギリスではなく、「カントリー」発祥の地アメリカ出身のバンド。ダブステップ興隆によってライブハウスからクラブへと向かったUKキッズの足並みに揃えるような、2010年代に差し掛かった頃のイギリスバンドシーンの低調ぶり、加えて去年ごろからのちょっとした復興を加味すれば、彼らFanfarloの特異さがいかほどのモノかが分かっていただけるだろうか。
ギター、ドラム、ベース、ドラムという基本的なバンドサウンドの横から差し込まれる、ヴァイオリンやトランペットという揺らぎに満ちた音色は、ゆったりと、牧歌的に、優美な縁取りを加えていくようにも聞こえる。いや、彼らに授けられる「オーケストラル・ポップ」という名前は、彼らにとっては本当に<縁取り>にすぎないと気付かされる、それが本作『LET’S GO EXTINCT』なのだ。
「僕らが書いた曲は、進化の理論が『僕らは一体全体どこにいるんだろう?そして何処に向かおうとしているんだろう?』という問いに答えようとしている事象を間接的に、もしくは遠まわしに扱っているように思えたんだ」(公式資料より抜粋)
これまではマルチプレイヤーであるメンバー5人操ってマンドリン、グロッケン、メロディカなどの室内楽楽器を操り、その特有の繊細さで聴く人を魅了してきたように思える。翻って本作、上述したバンド側の答えにもあるように、メンバー5人全員で調和し生んでいくバンドサウンドは一段と迫力と躍動感が増し、大きくうねる波のように聞く人を飲み込んでいくようだ。そこに光のアクセントのように室内楽楽器が差し込み、メンバーの音楽IQの高さから生まれるちょっとした突飛さも相変わらず、また一歩高みに登った快作となっているのだ。
少なくとも彼らがデビューした当時、彼らはインディーシーンの最前線にたつようなバンドではなかったのは確かだ。時は動き、Arcade FireやMumford & Sunsといったチェンバー・ポップ/インディー・フォークバンドがグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞、いま現在のロンドンやイギリスを包むバンド・ミュージックの流れとは寸断されているが、このフィールドにスポットライトが当たるタイミングがようやく到来したと言ってもいいだろう。そんななか、『LET’S GO EXTINCT(直訳:絶滅へと進もう 形容詞をムリに名詞として訳)』というコンセプチュアルなテーマを示唆したオルタナティブ・ミュージックを堂々と奏でる彼らは、まさにアーティスト、その本性が本作を快作にしたのだ。