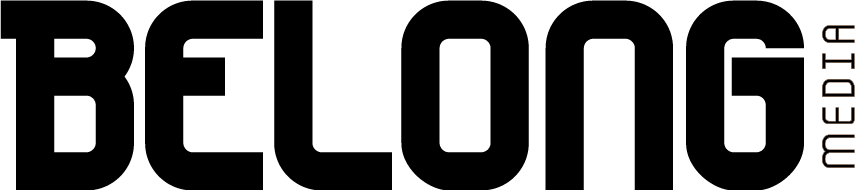最終更新: 2014年7月11日
昆虫キッズは不思議なバンドだ。所謂東京インディーのシーンの真ん中にいるのに、まるで東京インディーっぽくない。東京インディーというとやはりceroや森は生きている、そしてスカートみたいに、洗練されたシティポップ的な印象を抱きがちだ。しかし、昆虫キッズは全然違う。キーボード含むアレンジでもその曲はどこか不安定さと焦燥感に溢れ、そしてそれ以上に切迫と混沌を見せる歌唱・歌詞は、洗練とは逆の、どこか半狂乱の状態のまま(だからこそ)何か暴き倒してやろうという野心に満ちているように思える。
そんな彼らだが、その野心の表明の手法としての楽曲やサウンドは、リリースの度に進化していっていると感じられる。最近、特に東京インディーシーンでははじめから音楽性が非常に高く、作品を重ねても“進化”というより“変化”を感じさせるものが多い中、昆虫キッズのそれは紛れもなく“進化”であり、ベースドラム+ギター2本orギター+キーボードの編成で、作品を出すたびにネタ切れの様子も見せず「そのアレンジがあったか!」という新鮮な印象を抱かせてくれるのは、ギターロック好きとしても非常に頼もしい。
今作『BLUE GHOST』はそんな彼らの、全国流通盤としては4枚目となるアルバム。前作『こおったゆめをとかすように』はこれまでのバンドの進化の中でも特に目を見張るものがあり、バンドがパンクな方向にも抒情的な雰囲気にも独特の毒性を保ったまま自由に作品を形作っていた感があり、出色の出来だった。そこからの“変化”はどんなだろうと、ぼーっと口を開けて新作を聴いて、はじめ少し地味か、と思った。今作の大きな特徴のひとつは、昆虫キッズサウンドきっての飛び道具であるのもとなつよ氏ボーカルの“ほぼ全面的な封印”で、あの可愛らしくも鮮烈なボーカルが(先行リリースの「変だ、変だ、変だ」などごく一部を除いて)聴けないのは、それは少し地味に思われても仕方がないかもしれない。
しかし、その重大な“不在”の裏でまさに存在感を強大にしているのが、昆虫キッズの詩情の心臓・高橋翔の世界観である。印象的なジャケットに引っ張られる部分もあるが、今作の楽曲は何故だろう、これまで以上に、しかもこれまでになかったような“高橋翔節”のようなものを感じさせる。それは例えるならアルバム『Adore』の時期のビリー・コーガンのような、少しゴスくて落ち着いていて、しかしその内に妖艶なナルシシズムとロマンとを抱え込んだ具合だ。こんなにも彼の歌が美しく全体を支配している度合いは、名作だった前作ですらここまでではなかったはず。あるいは今回エンジニアを務めプロデュースにも影響を及ぼしたというカメラ=万年筆の佐藤優介氏がもたらしたものもあるのかもしれない。
冒頭「GOOD LUCK」のいきなり歌から始まる自信、次第にロマンチックな盛り上がりを見せる演奏、そこから軽快な「Metropolis」に連なる曲順の気持ちよさ。無骨なベースイントロに似合わずとても儚げで抒情的なメロディの飛翔を見せる「COMA」、バンドの攻撃性を重く冷たいサウンドに転化した「THE METAL」「ともだちが泣いている」からの今作で最も軽やかで爽快な演奏と歌唱を見せる「Alain Delon」への流れ(しかしこういう曲のドラム叩かせると佐久間裕太氏はなんて上手いんだろう)等々…。より高橋翔のロマンチズムが前に出た楽曲の質は前作に勝るとも劣らず、そして全体の雰囲気としては“特にこの作品”という独特のものをしっかり有している。
つまり、名作だと思う。とりわけ、高橋翔というソングライターの存在感や性質面での進化という意味で、今作は前作までとまた違った充実の仕方をしている。かのNUMBER GIRLのベスト盤か何かのライナーノーツには「ひとつのバンドで5年もしっかりやってればそのバンドですることはなくなる」みたいなことが書いてあった。それはともかく、昆虫キッズは2007年以来の活動の中、もがきと挑戦と成熟とを重ね、また素晴らしいアルバムを無事に新しい充実の中でリリースした。高橋翔は今年29だという。それは、とても素敵で頼もしいことのようにつよく感じられる。