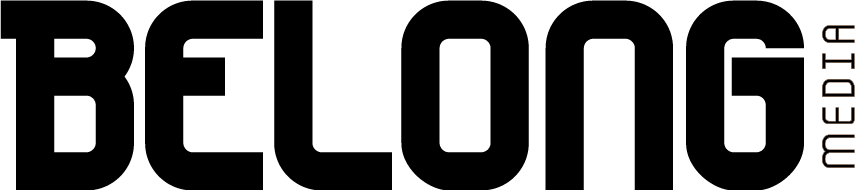最終更新: 2021年7月31日
2013年リリースのソロ前作『PIL』リリース時の、どこかのインタビューで、かのBlankey Jet Cityをはじめ幾つものバンドを立ち上げて日本のロックを振り回してきたベンジー=浅井健一は、“これからはもう、SHERBETSとソロの二つだけをやっていこうかと思ってる”といったことを話していた。(その後すぐに新バンドRomeo’s Bloodでフェス出演となったのはご愛嬌だけど。。。)この発言を僕は当初、SHERBETSはがっつりディープな感じにやって、ソロの方で(他の新バンドなんかに流れていってた)ブランキー的なキャッチーなロックンロールをしていく、と区別するものかと考えた。確かに『PIL』にはそんなキャッチーなロックンロール要素は近年でも大きかった。しかし同時に、SHERBETS的ともいえる内省的な雰囲気も多分に含んでいたことが、少々意外だった。
Nancy

そして今作『Nancy』において、彼の今のスタンスがよりはっきりしたように見えた。一聴、と言わずとも試聴器の前で何曲かをちょっと流してみるだけで分かる、今作のダークな雰囲気。ロックンロールを振り回す局面は相当に限定され、ひたすら感傷と虚無とを引き込んでいるようなマイナー調の楽曲の数々。それ自体が際立つというより、むしろ楽曲に進んで溶け込んでいくギタープレイの数々。囁くようなスタイルを中心に、時折まくり上げる声もメロディアスに纏められた歌唱。一際ニヒリスティックな視線が垣間見える歌詞世界。
一聴してすぐに思ったのは、この作品ひょっとしてこれまでのキャリアでも最もダークでダウナーな側面を担ってたSHERBETSの諸作よりもダークでダウナーなんじゃないか、ということ。そしてもしかしたら、最早ソロとSHRBETSは手法の違いであって、浅井健一の世界観はどちらでも同じところに向かおうとしているのではないか、二つの表現スタイルにて、自分の世界観を更に更に追求していこうと思う、ってことなのではないかと考えた(元々彼は「バンドや形式によって歌いたいことが全然違うってことはない」的なことも言っているが)。
前作からの一人打ち込み制作路線を爽やかに活用した一曲目「Sky Diving Baby」に始まり、シャープな曲調と奔放なイメージの中に殺人者に対する怜悧な視線を忍ばせる「Stinger」、悲劇の科学者というSFチックな悲哀が筋肉少女帯「機械」辺りと通じるものを感じさせる「Papyrus」、少し心配させる曲タイトルを見事予想の斜め上方面にポップで華やかに危うげにぶっ飛ばしてしまう「桜」、世界の破滅を予感させるかなりSHERBETSライクな先行公開曲「紙飛行機」に、そして遂に世界が破滅してしまった後のことを精一杯の健気さと浅井史上最も美しく残酷な一行(「やがて冬がやってきて/雪が全てを覆い尽くして/何もかもにとどめさされて/しまう前に」)を対置させて描く今作の最終曲「ハラピニオ」。今作の楽曲は特に曲のサイズやアレンジの点で普段以上に丁寧な印象を受ける。
浅井健一は日本の希代のロックンローラーであると同時に、尖鋭でかつ独自の進化を遂げた世界観を有する邦楽きっての詩人でもある。今作はその後者の側面について、ソロの立場から徹底的に取り組まれた作品。浅井健一の求道者的な精神さえ感じさせる。これを受けて楽曲の傾向的に同ベクトルであろうSHERBETSの活動が今後どうなっていくかも含めて、とても魔力的な作品だ。