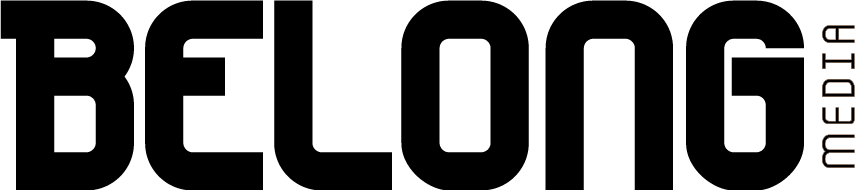最終更新: 2020年5月16日

大阪のライブバー「FAN DANGO」の店長の加藤氏は言う、「大阪のジャックナイフとは、ゆれるのこと」だと(公式サイトより)。
奄美大島出身のAmi、Yuta Sakaeの2人に、京都出身のBauchiが加入し、彼らは2011年ごろから活動を開始した。
今年の6月に3枚目の新作ミニアルバム『XENOtransplantations』が発売され、同時にこれまでに発売された2枚のミニアルバムが『distractions+』と『mutilations+』としてリマスターし、合計3枚のアルバムを今年発売。東京に負けず劣らず興隆を極める関西インディ界のなかで、ひときわ大きな波に乗っているバンドだ。
最近の邦楽ロックバンドが駆使する4つ打ち(イーブンビート)テクニックを使わず、何か別のジャンルとクロスオーバーして生まれたわけでもない、コード進行に合わせて轟音と轟音と打撃音がただぶつかり合うだけの、ロックンロールの爆音。それはメンバーの好みである、eastern youthやbloodthirsty butchersが透けて見えるほどの潔さを伴っている。
6本と4本の針金を備えた楽器を掻き、太鼓を5個か6個と薄い金物3枚を備えた鳴り物を叩く、そうして生まれるロックという音楽は、言うまでもなく金属音の塊だ。前言のジャックナイフという喩えもそうだが、そこから浮かび上がる金属の鋭い切れ味でもって身を切りつけられる衝撃、ロックという音楽が体現できようその感覚を、ゆれるは間違いなく体現している。
「僕は 不意に現れる焦燥感でさえも 悲観してるような気がして そしてどうでもよくなった」(赤い破壊 より)
「引き換え線からこうなったんだ 悪い塩梅のクレイジーソルト 引き返しても同じ味だった ならば俺は夏のことなんて知らない 知らなくていい」(クレイジーソルト より)
彼らを聴けば、00年代邦楽ロックが「焦燥感」によって包まれてしまった時期を自然と思い出す人も多いと思う。だがゆれるにとって、焦燥感は時として意味をなさず、拒絶と虚無を抱えこむ理由となる。彼らが爆音へと身を捧げる理由は分からない、けども、爆音へと身を捧げる一瞬を捉えようとしているからこそ、音と音の激突によってチリチリとした火花が生まれるような鋭さが保たれているような気がする。その熱が終わらぬうちに、彼らが放つ生の熱波にゆられていたいと思う。