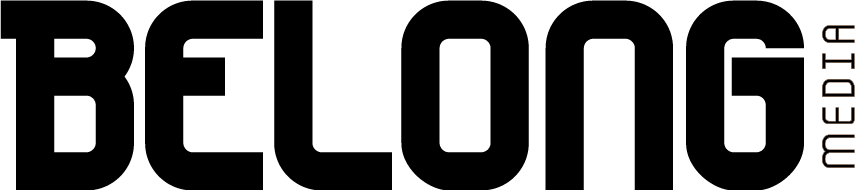最終更新: 2020年5月16日

貴方は昨年リリースされたdipの『neue welt』を聴かれただろうか。もし貴方が海外ないしは日本のオルタナティブロックやニューウェーブに興味があるなら、このアルバムを聴いて損することは決してないはず。この国で80年代末から所謂オルタナ・ギターロックサウンドを追求してきたこのバンドの、20数年のキャリアを経たくせに新境地めいた強靭なポストパンク風味のバンドグルーヴに焦点をぐっと絞った感のある、冷血怜悧かつがっつりオルがタナしている名作だ。
ところで、貴方はdipの歴代の楽曲が、どこか冷めたトーンは一貫して変わらないものの、そのトーンの下で実に様々な音楽性を孕んでいることをご存知だろうか。つまり、中心人物であるヤマジカズヒデは、基本Sonic YouthやPavementといったUSオルタナ勢のサウンドを基調とはしているが、しかしながら同時にThe Roosters的なロックンロールから、中期以降のThe Beatles的なサイケデリアなグルーヴ感、果ては昭和のフォークや歌謡曲のようなうねりのあるメロディまでを自身の血肉としてきた男である。
そんな彼がこの度リリースにこぎ着けた、正規流通盤としては実に21年ぶりとなるソロアルバム新作は、まさにそういった豊穣な音楽性のうち、特に近年のdipがソリッドな音楽性をストイックに追求するが故に零れ落ちた部分を滑らかに補完するような作品になっている。uminecosoundsで共演している須藤俊明氏との共同作業によってリラックスした雰囲気で作られた(この辺の事情は小野島大氏とヤマジ氏の対談記事に詳しく書かれている)という楽曲は、時にヤマジ氏のリリカルな歌もののセンスがコンパクトに表出され、または彼のサイケイズムがdipとは異なった形で表現されている。
そんな楽曲を聴いていて浮かぶのは、黒色の煙が淡々と、これといった意味もなくただゆっくり漂うような光景だ。しかしその光景には不思議な透明感があり、奥行きがあり、慎み深さがある。親しげな訳ではないが、かといって無愛想な音楽でもない。肯定も否定も、歓喜も絶望もない、ただなんかいいなって音楽。“純音楽”などと呼ぶことも憚られるそのさりげなさには、21年前のソロ諸作とも通じる、彼の中の空白と、それを色付けない程度に彩る器用に不器用なセンスがある。21年前と違うのは、その空白感から逆説的に醸し出される何らかの豊穣さであろうか。胸に広がる黒い煙は、貴方の中の透明な気持ちをぼんやり照らすだろう。こういう具合に透き通った気持ちというのも、きっとあるんだろう、あっていいんだろう。