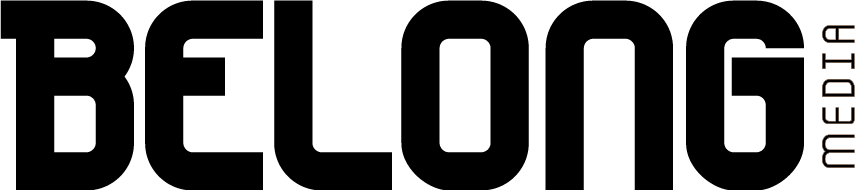最終更新: 2020年3月6日

今回の特集“YOUTHWAVE”では、物心のついた頃からインターネットへアクセスできる“デジタルネイティブ”の時代に生まれたアーティストを中心にインタビューを行った。
その中でもYkiki Beatは「Forever」の映像が公開されるやいなや国内だけでなく、海外にも大きなインパクトを与えた。
彼らが証明したのは日本人でも海外と対等もしくはそれ以上の音楽を作る事ができるという事だ。伝説のバンドBLANKEY JET CITYのベーシストである照井氏もYkiki Beatを評して、“日本のバンドとは思えないセンスを感じる。(中略)明らかにNew generationだと感じた。グラミー賞とか受賞する日本人アーテイストがこれから出てくるのかもしれないな。”と自身のブログに綴っている。
それではそのYkiki Beatは今、どんな事を考え、音楽を作っているのだろうか。メンバー全員に話を聞いた。
アーティスト:秋山 (Vo./ Gt.)、嘉本 (Gt./Vo.)、野末 (Syn./Vo.)、加地 (Ba./Vo.)、関口 (Dr.)インタビュアー:まりりん 撮影:Masahiro Arita
-バンド結成の経緯を教えてください。
秋山:簡単にまとめると、もともと僕ら全員大学が一緒なんですけど、最終的に同じサークルに入ったけど、別々のサークルにいて。音楽のサークルだったんで繫がりの繫がりで自分たちの好きなテイストの人たちを見つけて大学内で組んだのが一番最初ですね。
-バンド名の由来について教えてください。
加地:僕と秋山と嘉本がサークルに入り始めで、はじめにコピーバンドやってみようかってなって、その時のバンド名をつけるのにたまたま“ワイキキ”って言葉が出てきて、その当時、組んだバンドには使われなかったんです。でも秋山の心の中に引っかかるものがあったみたいで、このバンドを組んだ時にその言葉が使われました。
秋山:バンド名を付けるときに候補をたくさん作ってその中から組み合わせたり、変えたりして、どれがいいか判断しながらいつも決めてたんですよ。YkikiBeatのバンド名を付けるときにはBeatって言葉はシンプルだけどいいなってストックの中にあって。加地が説明してくれたみたいに“ワイキキ”って言葉も案にあったので、どういう風な流れでこれにしようってなったのかは覚えてないんですけど、言葉を組み合わせていく中でできた感じです。今だと“ワイキキビーチ”をもじったってよく思われるんですけど、当時は別にそんなことを考えてなかったんですよね。
-“Ykiki”のスペルも違いますよね。
秋山:それもわざと変えた訳ではなく、最初に“ワイキキ”って言葉が出たときに、頭の中で勝手にこのスペルに変換されてて。あとで考えたら絶対おかしいんですけど、頭の中にYがパッと出たときにちょっとトリッキーで言葉遊びみたいな感じがして。当時はそういうバンド名が多かったんで、それはそれで面白いかなって採用しました。
-以前から注目を浴びていましたが、このタイミングでアルバムを発売しようと思ったのはどうしてでしょうか。
秋山:大学2年の時に結成して活動していたんですけど、卒業したら何人かのメンバーは就職して、バンドはあんまり活動できなくなるだろうと思ってて。そもそも卒業前、今年の3月の前にリリースしようとしていたんですけど、卒業までの流れの中でバンドが調子良くなってきていてもう少しバンドを続けようということになったので、内定をもらっていたメンバーも内定を辞めたりして。それだったら焦って3月までに作る必要はないかなって事で、レーベルの方にも時間をもらいながら、なるべく早く出したいってって中で1番早く出せるタイミングがこの時期だったって感じですね。
-なるほど。アルバムタイトルの『When the World is Wide』に込められた意味について教えてください。
秋山:アルバム名は象徴的な意味合いを持たせられる、解釈の幅があるものにしたいと思っていたんですよ。一つの説明に収めたくないんですけど、一つの大きな意味としては、“When the World is Wide”を省略すると“WWW”でちょっとインターネットを比喩していて。インターネットができてから世界が広くなったっていうか、“World Wide Web”で世界が広くなったとも捉えられるんですけど、逆に言えばインターネットのせいで色んなことを疑似体験することができるようになった分、どの世界の人も近くなってしまったんじゃないかと思います。Facebookで簡単に繋がれるようになったり、誰と誰が共通の友達でどんどん世界が狭く感じられるようになってきていて、本当にインターネットが世界を広くしているのか俺は分らないなって思った。アルバムタイトルはそういった象徴的な意味として持ってきたのと、直訳の意味としては“世界が広かった時”。それは今というよりはどこに限定しているわけではなく、過去か未来か今か。でも本当に今、時代がどんどん良くなってるっていう風に思ってる人は少ないと思うんですけど。ちょっと考える余地のある時代の流れに疑問を投げかけるようにしたいと思ってこのタイトルにしました。
-これは秋山さんが考えたのですよね。他のメンバーは“世界が広かった時”っていつだと思いますか。
野末:原始時代とか、逆に世界が狭かったかな。
秋山:幼稚園に行く頃にはWindows95があって、インターネットの存在は小さいころから感じていたと思うんですよ。でも今、みんながYoutubeで同じ動画見て、Googleで検索してというほど同じような情報を共有してなかったと思うんですよ。あの時の空気を感じるとやっぱりもう少し未知の部分があったというか、インターネットを調べてもすぐ見つからない情報があったし、自分たちが小さかったというのもあるけど、あの頃はミステリーな領域があったと思うので。おそらく自分の親の世代まで遡れば、もっと知らない世界が多かったのかなと思っていて。この10~20年で大きく変わってると思うんですけど、原始時代まで遡らなくても(笑)。でも島の外、村の外に出ないって時代まで遡っても、今度はその人たちのコミュニティはここだけになっちゃうし。定義はないと思うんですけどコミュニティの広さとか狭さに。

-シュールレアリスムで世界を表現したのようなアートワークだと思ったのですが、アルバム制作時にこのようなイメージがあったのでしょうか。
秋山:前はアートワークも自分たちでやってたんですけど、今回はだいたいのイメージを伝えて、YOSHIROTTENっていうクリエイターの人に頼んだんですよ。頼んだときもこんな感じで、こんな色でってとこまで指定した訳ではなくて、自分たちがアルバム作る中でのイメージや歌詞とか、アルバム全体の説明をしてイメージくらいは伝えたけど、あとはやってもらったって感じですね。確かにシュルレアリスムっぽさはあるけど、それは自分たちが要求したものではなくてYOSHIROTTENさんがたくさん出してきた案の中でこのアートワークだけひときわ目立つところがあって。色合いも目を引くところがありますし、ちょっとコンセプチュアルなところがあるので、これを選びました。アートワークに関しては、それだけで何かを表現しようとは思ってなくて。“東京っぽさ”は出してほしいとお願いしました、“日本っぽさ”ではなくて。できるだけニュートラルでどの国のバンドにも通用するような質感なんだけど、“東京っぽさ”は出してほしいと。自分たちの目指していたところになったかなと思います。
-そこで東京にこだわったのはなぜですか。
秋山:ずっと活動していたのが東京っていうのもありますし、アメリカやイギリスの音楽に影響を受けているとはいえ、UKのトラディッショナルな服を着て写真を撮ってもアメリカの西部の格好をしても、やっぱり違和感が生じちゃう分、東京のスタイルも世界から見たらかっこいいと思えるポイントがたくさんあると感じるんですよ。どうせなら自分たちでないものになるよりは、アートワークにしても考え方にしても東京なりに世界を解釈したやり方で、フラットな視点で他の国が見てもかっこいいと思えるものが作りたかったんです。音楽に関しては特に。東京らしさを特別フューチャーしたかったわけではないんですけど、いい形で解釈しながら音楽にもアートワークにも出せたらいいなと考えてました。
-Ykiki BeatはDYGLと兼任しているメンバーが多いですが、秋山さんは曲を作るときにそれぞれ区別しているのでしょうか。
秋山:それは大きな問題で、自分たちもよく考えてるんですよ。このアルバムの前までは意識してDYGLの曲、Ykiki Beatの曲ってやることが多かったんですけど、今は明らかに作ってる時点でどっちの曲って分かってる場合もあるんですけど、とりあえず作ってみて。この曲はどっちのバンドでやるほうが説得力あるかなって、後から考えることも増えてきてて。自分だけで作ると自分の中だけの判断になるので。同時にセッションで作ることも増えてきたので、その場合はそのセッション内でできたほうのバンドで。当たり前と言えば、当たり前なんですけどそういう風に分けてます。明確な決まりはないんですけど、その楽曲が説得力を持つほうでやりたいって思います。
-「Dances」は秋山さんと嘉本さん2人で制作されていますね。どのように曲作りに関わっているのでしょうか。
嘉本:あんまり覚えてないですね。たまに一緒に作ることがあって、それの一部みたいな感じですね。
秋山:このアルバムの前までは彼が曲を作ってて。このバンドを組むきっかけになったぐらい1番最初にできた「London Echoes」って曲があるんですけど、それもそもそも彼が15秒くらいのループの音源を作ったものがあって。それを俺が聴いたときに可能性がある曲だなって思って、そのフレーズをもらって展開して歌をのせて作ったんですよ。それがYkiki Beatのはじまりのきっかけになった曲なんですけど。それがあってBandcampで売ったり、会場でリリースしていたときの音源は半分くらい彼が作ってきたものを僕が展開させてできたものだったりするので。それから後はバンドとしてのイメージをどうしようっていうのがさらに混沌としてきたので、一緒に作業するというよりはそれぞれで考えることが多かったんです。アルバムを作るに当たって、もう一度最初のやり方でやってみようってなった時に彼が色んな音源を送ってきてくれた中で、広げて曲になったのが「Dances」だったんですよ。アルバムから新しいチャレンジではなくて、昔からのやり方を今やってみたって感じです。
加地:他の3人が曲作りに関わったことは今までないですね。セッションで作るときはアレンジしたりしてるんで、そういう部分ではみんなで作っています。
秋山:採用にはなってないんですけど、加地が自分でフレーズなり、歌の種みたいなのを作ってくることも何回かあって。もしかしたら今後別の形もあるかもしれませんね。
-国内外から高評価を受け注目されていますが、環境に変化はありましたか。
秋山:国外からの反応はたまにメッセージをもらったりぐらいで実感としてはあまりないんですけど、どれくらいの人が聴いてくれてるとかも知り合いの範囲でしか分らなくて。国内で言えばインターネットの反響にしても扱ってくれる店舗の展開にしても、今までに体験したことのない大きさなので、そういう意味で言えばバンドとしてはかなりいい状況なのかなって思いますね。結局、自分たちの物作りの能力みたいなのが伸びていかないと、何の意味もないので。それはそれでバンドを広める面と自分たちの創作の面とを分けて考えないといけないと思っているので。まだこれぐらいしか到達していないと自分たちが思っていて、過大評価をされていると思うこともあって。正直に言うとちょっと戸惑いがあるにはあるんですが、それは自分では選べる訳じゃないので。そこはある程度割り切るじゃないですけど、横目に見るくらいの感覚で。あとは自分たちの納得のいく作品を作りたいって気持ちは変わっていないですし、何なら前よりもっといいイメージが増えてきているくらいで。周りの反応はそこまで重視していないですね。もちろんバンドにとってはサポートしてくれる人が多いってのはバンドを続けるモチベーションにもなるし、いい影響はかなりあると思います。
インタビュー後半はこちら