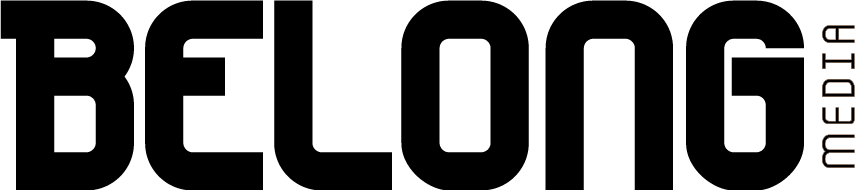最終更新: 2024年7月14日
2020年の年間ベストソングを選ぶにあたって思ったのは、昨年は音楽の転換期と言っても過言ではない年だったことだ。
ライブの開催が難しくなり、アーティストやリスナーにとって厳しい年だったが、かえって目立ったがライブ音源、カバー曲、コラボ曲の3つ。
コロナ禍と言われ良くない部分ばかり注目されがちだが、これらの部分に目を向けてみると普段では聴けないもの、見れないものを見れた年とも言い換えれないだろうか。
そんな過去に例がない年について、選曲した音楽とともにどんな音楽を聴いてきたか振り返ってもらえると幸いだ。
年間ベストソングプレイリスト
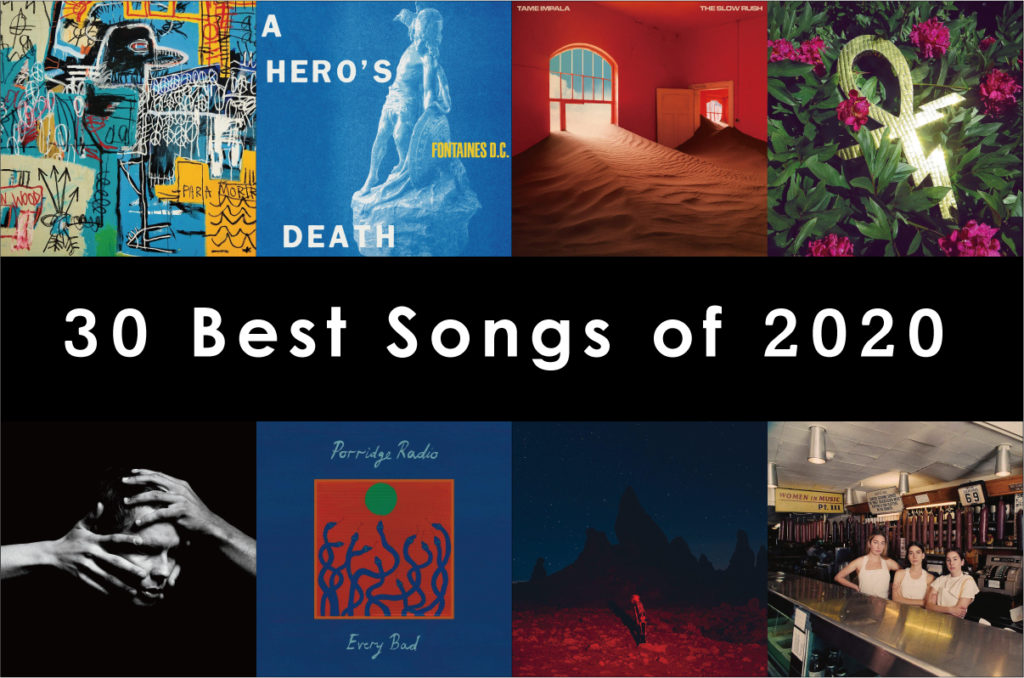
The Strokes「The Adults Are Talking」
昨年の年末、“世界的なカムバックを果たす”と宣言したThe Strokes(ザ・ストロークス)。
その予言は実現し、前のアルバムから7年間の沈黙を破るにふさわしい新作『The New Abnormal』とともに帰ってきた。
「The Adults Are Talking」はこれまでにない5分を超す楽曲であるものの、そこで鳴らされているのはメンバー間の楽器を通した会話であった。
それゆえこの曲を聴くだけでも、新作アルバムが間違いないものだと確信できる1曲。(yabori)
Washed Out「Paralyzed」
Washed Out(ウォッシュト・アウト)は一貫して自分の音楽は“逃避である”と言い続けてきた。
新作アルバム『Purple Noon』で彼はチル・ウェーブを定義したデビューアルバム制作時のレーベル、プロデューサーに回帰し、新たな地平を目指すことに。
その成果は「Paralyzed」に最も現れており、打楽器と鍵盤で奥行きとリスナーにまだ見ぬ景色を見せることに成功した。(yabori)
Gorillaz「Strange Timez (feat. Robert Smith)」
Gorillaz(ゴリラズ)の新作アルバム『Song Machine』は超弩級の作品だった。
特にThe Cureのロバート・スミスとコラボした「Strange Timez」は不吉ながらもポップさが光る。
これぞゴリラズ!と言える曲にロバート・スミスのボーカルの合うとは夢にも思わなかった。
ロバート・スミス使いが余りにも秀逸な同曲のMVも必見!(yabori)
The Killers「Fire In Bone」
The Killers(ザ・キラーズ)の『Imploding the Mirage』はベテランバンドの新生を感じさせる感動的なアルバムとなった。
それには今作に参加したFoxygenを始めとする若手の力も大きく作用しているに違いない。
そんなアルバムの中でも「Fire In Bone」は炎のゆらめきをあでやかなギターで表現している。
これぞ新たな到達点であるとリスナーに鮮烈な印象を与えた。(yabori)
Marilyn Manson「WE ARE CHAOS」
Marilyn Manson(マリリン・マンソン)の新作アルバム『We Are Chaos』は期せずして、この混沌極まりないコロナの時代にリリースされた。
本人いはくタイミングを合わせた訳ではないそうだが、そうでないにしても余りにもでき過ぎた話だ。
「WE ARE CHAOS」は聴き手を混乱の底に叩き落すと同時に救いの手を差し伸べる。
これぞマリリン・マンソンの本領発揮と言えるアンセムを全人類にお見舞いしてくれた!(yabori)
Haim「Summer Girl」
今年は最新アルバム『Women In Music Pt. III』が軒並みベストアルバムに選ばれたり、テイラー・スウィフトの新作に参加したりと大きな注目を集めたHaim(ハイム)。
新曲「Summer Girl」は極めてシンプルで装飾をそぎ落とした楽曲が光る。
どんなシーンにも溶け込む透明感があり、聴くシーンを問わないというのもこの曲の良いところ。(yabori)
Fontaines D.C.「A Hero’s Death」
目の覚めるようなデビューアルバムをリリースし、UKロックの復活を期待させたFontaines D.C.(フォンテインズDC)。
新作アルバム『A Hero’s Death』はその期待を超え、全英チャート2位に輝いた。
アルバムタイトル曲の「A Hero’s Death」はざらついた生々しい演奏と風変わりなコーラスが繰り返され、ともすれば退屈になる一曲。
しかしそれを徐々に熱気に変えていくのがたまらない。(yabori)
Soccer Mommy「circle the drain」
昨年はJay Somを始め、女性アーティストの躍進ぶりと楽曲のクオリティに驚かされたが、今年の主役はSoccer Mommy(サッカー・マミー)だった。
新作アルバム『Color Theory』は自身の感情の起伏がテーマで、豊かなメロディーの中に悲しみも映り込む。
「circle the drain」はグランジロックの質感に淡々と歌うボーカルがとても心地よく、リスナーに適度な距離感で寄り添ってくれる。(yabori)
Parcels「Myenemy – from Hansa Studios, Berlin」
Parcels(パーセルズ)と言えばDaft Punkにプロデュースされた新星バンドという紹介がついて回る。
しかしそんな説明はしなくとも彼らの実力は『Live Vol.1』で存分に証明してしまった。
「Myenemy」はモータウン・サウンドとエレクトロ・ポップの良いとこ取りした1曲。
しかもデヴィッド・ボウイも使用したハンザ・スタジオで極上の音質で聴くことができるという・・・。ため息もの贅沢がここに。(yabori)
Sunset Rollercoaster「Candlelight (feat. OHHYUK)」

世界中で1000万回以上再生され、世界的なブレイクを果たしたSunset Rollercoaster(サンセット・ローラーコースター、別名:落日飛車)。
最新アルバム『Soft Storm』に収録された「Candlelight」ではHYUKOHのOHHYUKを迎え、本格的に世界へ打って出る清涼かつ不穏なサウンドを磨き上げている。
誰も見たことのないアジアの風景を丁寧に描いたMVからも自分たちが文化の発信者であるという自負が感じ取れるのではないか。(yabori)
Temples「Paraphernalia」
ショーン・レノンをプロデューサーに迎えて制作された「Paraphernalia」。
Temples(テンプルズ)らしからぬモダンなビートとレトロ・サウンドの対比は、時代にフィットしながらも自身のヴィンテージカラーを色濃く反映していて見事。
空間を巧みに埋める効果音の装飾やボーカルのエフェクトがかなり凝っており、何百回と聴いたが今だに新たな音を発見をさせてくれる深さがある。
サイケデリック新時代の夜明けにふさわしい。(Rio Miyamoto)
Blossoms「The Keeper」
時代の変化に合わせたポップ・ソングを次々と生み出す根っからのポップ・ボーイズことBlossoms(ブロッサムズ)。
「The Keeper」で参加しているコーラス隊が生み出すソウルフルなゴスペルとポップスのバランスが秀逸。
この曲から見えるのは、愛や平和といった万人が求める理想郷のような風景である。
ポップのど真ん中をストレートに撃ち抜き、アーティストとしての大きな進歩を感じるBlossomsの今後が楽しみで仕方ない。(Rio Miyamoto)
HAIM「The Steps」
HAIM(ハイム)のアルバム『Women In Music Pt. III 』はとにかく驚愕だった。
今までファッションにメイク、歌い方などキャラクター作りを完璧にこなしていた彼女らが、突如ノーメイクで内側の美を曝け出してきたような感覚だ。
飾り気のない、ただ純粋に良質な音楽を作りたいというミュージシャンシップが存分に注ぎ込まれた「The Steps」。
これはもしかすると“音楽の真髄”なのでは?、と考えさせられる一曲。(Rio Miyamoto)
Inhaler「We Have To Move On」
2020年代を代表するInhaler(インヘイラー)のロックアンセム「We Have to Move On」。U2ボノの息子という期待をいとも簡単に裏切ってきた。
“若さを自覚した青少年”という表現がしっくりくるのだが、若いうちにしかできないことをその年で理解しているのが憎たらしくも羨ましい。
だが決して子供っぽいわけではなく、誰にも止められないスピード感と圧倒的なオーラが共存した若きロック・スターがここに誕生したことをこの曲で証明した。(Rio Miyamoto)
Tame Impala「Borderline」
サイケデリック界の最高峰として君臨するTame Impala(テーム・インパラ)。ダンサブルな音楽性へ舵を切った『The Slow Rush』。
ファンの間でも賛否両論あった今作だが、その中でも「Borderline」は以前のサイケデリアを大人の色気で包み込んだ、まさに“新旧の橋渡し”的なポジションになる曲だろう。
近年のコラボ活動で培われた、多彩なジャンルを織り交ぜた独自のサイケデリアはその彩りを増し続けている。(Rio Miyamoto)
Bibio「Sleep On The Wing」
Bibio(ビビオ)は大自然をそのまま音楽としてパッケージングして届けてくれるアーティスト。
イギリスの田舎で録音された大自然の環境音、アナログ機材によって生み出されるノスタルジックな“Bibioサウンド”は「Sleep On The Wing」でも健在。
テーマであるアマツバメのように、イギリスの田園風景を眼下に見下ろしながら軽やかに飛び回る浮遊感もたまらない。
この曲を通して架空の大自然へと思いを馳せて欲しい。(Rio Miyamoto)
Thundercat「Dragonball Durag」
グラミー賞にノミネート経験のある天才ベーシストことThundercat(サンダーキャット)。タイトルの時点でドラゴンボールへの愛が炸裂している「Dragonball Durag」。
そんな日本人にも馴染みやすいユーモア溢れるセンスとは裏腹に、R&Bやソウル、ファンクを主軸にしたフォーマルな音楽性とのギャップに心掴まれる。
ベースラインが秀逸なのはもちろん、シンガーとしての表現力とメロディーの美しさにも圧倒される。(Rio Miyamoto)
Yumi Zouma「Lonely After」
Yumi Zouma(ユミ・ゾウマ)は作品を生み出すごとに音の透明度をどんどん上げてくる。
どれ程磨き上げるとここまで煌びやかな楽曲が生まれるのか、と疑問に思ったのが「Lonely After」だ。
サウンドデザインの面でも、全ての楽器隊をボーカルの声質に合わせに行ったような、“完璧な音のマッチング”が体感できる。
鳴っている一つ一つの音に意図が感じられるのもさすが。混じり気のない純度100%の音楽がここにある。(Rio Miyamoto)
Khruangbin「Time (You and I)」
エキゾチックなタイ・ファンクを現代に継承するKhruangbin(クルアンビン)。グルーヴを重視していた従来のスタイルが派生し、ヴォーカルがより際立った「Time (You and I)」。
歌メロ重視のポップス文化を取り入れながらも、“That’s life”というキャッチーなフレーズはヴォーカルを一つの楽器隊として成立させている。
国境の無いストリーミング時代だからこそ、本物の“ワールドミュージック”を体感して欲しい。(Rio Miyamoto)
Phoebe Bridgers「Kyoto」
Phoebe Bridgers(フィービー・ブリジャーズ)は闇をありのままに表現する女性シンガーソングライター。
「Kyoto」を初めて聴いた時あまりのポップさに目を見張った。
その軽快な明るさと反比例するかのように歌詞ではインポスター症候群について歌われているのが彼女らしい。
これまで影の部分に比重が置かれていたが、光の部分にも積極的にフォーカルを当ててバランスを取ったPhoebe Bridgersのチャレンジ精神に拍手を送りたい。(Rio Miyamoto)
Jonsi「Swill」
Sigur Rósのフロントマン、Jonsi(ヨンシー)が10年ぶりにソロ作品をリリース!
というだけでも十分嬉しいサプライズだったのだけど、やはりその内容も驚きの連発であった。特にこの「Swill」は、構築美と破壊のせめぎ合いが見事。
チェンバーポップを土台にエレクトロニカで、抒情的にその綺麗な音像を時に暖かく、時にむごく汚しながら想像を絶する果てしない空間を演出する様は圧巻だった。(滝田優樹)
I Break Horses「Silence」
ドリーム・ポップを凹凸感のある触覚的な音作りでかたどったI Break Horses(アイ・ブレイク・ホーセズ)の「Silence」は、6年ぶりのアルバム『Warnings』収録されている。
今作はBeach HouseやTV on the Radioを手がけたクリス・コーディがプロデューサーを担当。
陶酔的にメロディーを纏わせつつ、音の生々しさはそのまま。曲の後半にはデジタルとアナログなパーカションが渦巻く高揚感も含めて均整感の取れた美しい1曲だ。(滝田優樹)
Oneohtrix Point Never「Long Road Home」
2020年の個人的な音楽鑑賞は、Oneohtrix Point Never(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー)とThe Weekndで1/3を占めた気がする。
それぞれ今年に発表した新作アルバムには互いにプロデューサーとして携わっている。
「Long Road Home」においては、クラシック音楽と現行R&Bとの邂逅と切り張りされたサウンドの交響が冴えており、先鋭的であるのに心地いいのは両者の連携があってこそだ。(滝田優樹)
The Japanese House「Dionne (feat. Justin Vernon)」
2020年は、ジャスティン・ヴァーノン活躍の年でもあった。Bon Iverでの新曲リリースやTaylor Swiftの新作アルバム2枚へのゲスト参加。
そして、一番の活躍は「Dionne (feat. Justin Vernon)」である。
彼の代名詞であるボコーダーを使用してのヴァーカルは、The Japanese House(ザ・ジャパニーズ・ハウス)が鳴らす天然由来なエレクトロサウンドと暴力的な破滅音との繋ぎを担っており、対比と諧調をも強調する。(滝田優樹)
Kelly Lee Owens「Re-Wild」
Kelly Lee Owens (ケリー・リー・オーウェンス)の新作アルバム『Inner Song』は、Radiohead の「Weird Fishes/Arpeggi」をインストゥルメンタルアレンジしたり、John Caleがゲスト参加したりなど、挑戦の1枚となっている。
なかでも「Re-Wild」は、前作から引き続き幽玄なテクノを聴かせてくれるが、遅滞感のあるビートで音の隙間をぐっと広げ、
声と音の余韻を楽しませてくれる才色かつ、大人の色気すら感じる白眉の1曲。(滝田優樹)
Perfume Genius「Without You」
Perfume Genius(パフューム・ジーニアス)の新曲「without you」は、これまで以上に特異さとしなやかさ、そして輝きを増した開放的な曲だ。
ローファイなアコギの音色やストリング、ピアノなどを手繰り、典雅なバロック・ポップをインディー・ポップと融合し、賛美歌のような荘厳さを演出。
所々掠れ声を挟んだ軽快な歌声で高らかに歌いあげる素朴な装いで、子守唄のような優しさも兼ね備えた、味わい深い曲となっている。(滝田優樹)
Sorry「Snakes」
black midiやSquidらの登場で盛り上がりを見せるノース・ロンドンのインディシーンの新鋭Sorry(ソーリー)。
待ちに待ったデビュー・アルバム『925』をリリースしたことも忘れてはならないトピックだ。
収録曲「Snakes」の中心にあるのはポストパンクやグランジの旋律であるが、ダークなアンビエントやエレクトロニカの断片なども織り交ぜた先進性には新人ながらロックの未来を託したくなるような信頼感がある。(滝田優樹)
Phoebe Bridgers「Halloween」
Phoebe Bridgers(フィービー・ブリジャーズ)の「Halloween」が収録されているアルバム『Punisher』のジャケ写や同じく収録曲「Kyoto」のMVでも着用しているガイコツスーツ。
アルバム全体の色合いとしては緻密なアレンジが光りながらも開放的で音の色彩豊かなナンバーが立ち並んでいた。
そんな中、唯一ダークゴシックな情調で弦の質感を感じられるほどにストリングスを静謐に聴かせているのがこの曲。
ガイコツを象徴し、アルバムの出来栄えも反映。ゆえにこの曲を選出した。(滝田優樹)
Porridge Radio「Long」
ブライトン出身の新人ポストパンクバンド、Porridge Radio(ポリッジ・レディオ)。
HiNDSやStarcrawlerといった独特な女性ヴァーカル擁して激情的なギターとドラム、ベースを打ち鳴らす新人バンドは少なくないが、彼女らはそのタフさを持ちながら、強かなバンドだ。
同一のリフを繰り返しながら後半にかけて混沌した展開へと向かっても音一つ一つが粒だって聴こえる。
新しさは感じなくてもこのような細やかな配慮は誰にでもできるわけではない。(滝田優樹)
Jordana「I Guess This Is Life」
Soccer MommyやClairoの登場でベッドルーム・ポップシーンも活況を呈するが、2020年はまた一人Jordana(ジョーダナ)という新星が現れた。
アメリカはカンザス州を拠点とする19歳のJordanaは、丸みのあるエレクトロと快活な生楽器を新鮮な響きなまま届けてくれる。
上記2名のようにまどろんでしまいそうなサウンドが魅力で、眠りへと誘うものとするなら、Jordanaは目ざましのベッドルーム・ポップである。(滝田優樹)
ライター:yabori

BELONG Mediaの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。
ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻
これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。
過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。
それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行してきた。
現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。
今まで執筆した記事はこちら
Twitter:@boriboriyabori
ライター:Rio Miyamoto(Red Apple)

BELONG Mediaのライター/翻訳。18歳から23歳までアメリカのボストンへ留学し、インターナショナルビジネスを専攻。
兵庫県出身のサイケデリック・バンド、Daisy Jaine(デイジー・ジェイン)でボーカル/ギターと作詞作曲を担当。
2017年には全国流通作品である1st EP『Under the Sun』をインディーズレーベル、Dead Funny Recordsよりリリース。
サイケデリック、ドリームポップ、ソウル、ロカビリーやカントリーなどを愛聴。好きなバンドはTemplesとTame Impala。趣味は写真撮影と映画鑑賞。
今まで執筆した記事はこちら
ライター:滝田優樹

1991年生まれ、北海道苫小牧市出身のフリーライター。TEAM NACSと同じ大学を卒業した後、音楽の専門学校へ入学しライターコースを専攻。
そこで3冊もの音楽フリーペーパーを制作し、アーティストへのインタビューから編集までを行う。
その経歴を活かしてフリーペーパーとWeb媒体を持つクロス音楽メディア会社に就職、そこではレビュー記事執筆と編集、営業を経験。
退職後は某大型レコードショップ店員へと転職して、自社媒体でのディスクレビュー記事も執筆する。
それをきっかけにフリーランスの音楽ライターとしての活動を開始。現在は、地元苫小牧での野外音楽フェス開催を夢みるサラリーマン兼音楽ライター。
猫と映画鑑賞、読書を好む。小松菜奈とカレー&ビリヤニ探訪はライフスタイル。
今まで執筆した記事はこちら
他メディアで執筆した記事はこちら
Twitter:@takita_funky