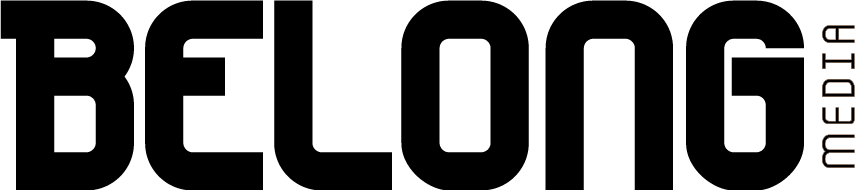最終更新: 2025年10月7日
新曲のみのライブで見えた次なるステップ

秋山信樹:そうですね。どういうライブをしようか、という話はしました。音源の面でも、自分たちが聴いて好きなもの、“好きだけれど、自分たちのバンドとしてやりたいわけではないもの”など、自分たちの感覚に改めて向き合いました。自分たちが本当にやりたいこと、それに近いアイデアやバンド、サウンドイメージと、逆に好きから遠いものを書き出して整理したんです。その中で気づいたのは、すごく叙情的で、重苦しい気持ちになるようなものは、今の気分ではないな、ということ。そういったことを制作の中でやったので、ライブでも“パフォーマンスとしてもう少しこうしたい”という話がしやすくなったり、自分たちを客観的に見れるようになった。とはいえ制作に比べると、まだライブは伸びしろがあるかなという印象ですね。でも、どちらの面もかなり成長を感じます。
-まりりん:ライブの本数も多いですよね。常に活動しているイメージがあります。
秋山信樹:常にライブをやっているイメージは確かにあるかもしれません。ですが、欧米のバンドだとツアーが始まれば1ヶ月で25本とか、ヨーロッパを3周するということもよく聞く話で。そういう叩き上げのバンドを見ていると、自分たちはまだまだやっていないな、と思いますね。でも、決して少なくはないと思いますし、常に動いている実感はあります。今日もライブだし、一昨日もライブだったし。
下中洋介:同じエリアでライブをやりすぎると、お客さんが分散してしまうということがあるので、そういうことがなければもっとやっているのかもしれないです。多いという自覚がなかったので驚きました。
秋山信樹:ただ、コミュニティによって、例えばハードコアのシーンなどでは、同じエリアでたくさんライブをやっていますし、本当に活動が少ないバンドは月1回でも多い方、というバンドもいると思います。どこを基準にするかですよね。
日本のシーンとDYGLの現在地

「立ち位置は考えたくない」――世代も場所も超える音楽の力
-まりりん:私がレコード会社にいた時、若いバンドから“DYGLのような活動がしたい”という声をよく聴きました。
秋山信樹:そうなんですか。放蕩息子たちが好き勝手やっている活動ですが(笑)。でも嬉しいですね。
-まりりん:日本のバンドシーンの中で、“自分たちでもDYGLのようになれるかもしれない”という一つの希望のようになっているのかな、と。
秋山信樹:嬉しい。逆にインタビューしたい(笑)。
-まりりん:ご自身たちでは、今の日本のシーンの中でどういう立ち位置にいると考えていますか?また、逆にDYGLにとって希望になるようなバンドがいれば教えていただきたいです。
秋山信樹:日本の中で、ですか。うーん…。基本的に立ち位置、みたいなことは考えたくないですね。そもそも音楽は必ずしも相対的にやるものでもないと思いますし、“何かを背負う”とか“シーンを引っ張る”みたいな意識でやりだすと、わざとらしくなってしまう気がして…僕が好きなバンドは、いつもその人たち自身が本当に好きなことをやっているな、と思える人たちなので。そういう人たちには、自然で等身大の魅力がある。世代の上も下も関係ないかな。音楽の魅力は、世代も場所も超えるものだと思う。だから、今この瞬間だけの日本の中での立ち位置なんかを考え出すと、凄く視野が狭くなってしまう気がします。変に「先輩」「後輩」みたいな小さな世界で音楽をやるのは、僕らのやり方ではないかな、と。コミュニティの中で、萎縮して自由に才能や情熱を表現できなくなってしまう人がいるのは楽しくない。
下中洋介:好きな音楽をやって、それを実際にどう広めていくか、ということをサポートしてくれる周りのスタッフも含めて、バンドだけの力ではできないです。やはり音楽が好きな人がそのバンドをサポートしてくれる環境が一番良いと思うので、そういう環境が増えたらいいなと思います。自分たちのことに関しては、ロールモデルがいたら良いのにと思う時もありますね。いないから仕方ないですし、いたとしても多分その人たちを目指さないとは思うんですけど、“お手本”のようなやり方があったらいいな、と思うことはあります。
秋山信樹:いつの時代でも、これだけ変わった職業ですから、みんな最終的にはオーダーメイドというか。同じ70年代同士でも、QueenとPink Floydでやり方は違ったでしょうし、どんなアーティストもみんな活動の仕方、正解は違うと思います。住んでいる街でも生活の仕方は違うし、車社会の街なのか、自転車で暮らせる街なのかでも音楽の形は変わる。活動の仕方に一つの正解があって、それをみんなが追うというよりは、それぞれが良いアイデアを出し合って、“こっちを試してみよう”“あっちを試してみよう”とできる方が楽しい。日本の中でDYGLが参考にされるにしても、逆に僕らが誰かを参考するにしても、最終的にはみんな自分たちバージョンの方法を見つけることになる。面白い動きをしているな、とアイデアやエネルギーをもらっているバンドで言うと、Texas3000は楽曲もすごく好きですし、面白い会場や座組でライブをしたり、ありきたりに収まらない動きをしているのを見て刺激を受けています。こちらも何かやろうという気持ちになりますね。
-まりりん:Texas3000はバンドからの支持が厚い印象がありますね。
下中洋介:彼らは、企画の面白さや曲の面白さで、きちんと結果を出していますよね。シンプルに“良い対バンを組んで、面白い場所でライブをして、良い作品を作る”という。それができる稀有なバンドだと思います。
次のページこちら ⏩️