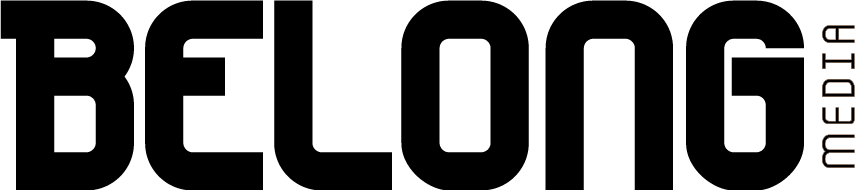最終更新: 2019年10月4日
OGRE YOU ASSHOLE

アーティスト:出戸学(Vo.,Gt.)、清水隆史(Ba.) インタビュアー:yabori
-アルバム制作には2年かかったそうですね。時間をかけて作られたと思うのですが、どのようなところを工夫したのでしょうか?
出戸:構想はあったんですけど、実際作業に取り掛かったのは去年の年末くらいからですね。曲作りを始めて、スタジオに入ったのは今年4月が最初です。
-ということは構想を作る期間が長かったんでしょうか?
出戸:どういうことをやろうかっていうのは、作業に取り掛かる前後でちょっと変わったりして。最初はミニマルなインダストリアルっぽいノイズとか、エクストリームな音にしようかっていう話があって。そこから変わっていって、ミニマルに加えてメロウな要素を入れようってなったのが去年の年末くらいですかね。だからもっと早いタイミングでアルバムを出していたら、もうちょっとエクストリームなノイズの要素が多いものが出来たかもしれない。
-今回そのどっちの要素があるように思います。
出戸:メロウな要素とミニマルな要素、どっちもあると思います。
清水:雰囲気は若干、ポストパンクな感じになってるのかもしれません。
-今回のアルバムは同じフレーズの繰り返しが多く、必要最小限な音で踊らせるアルバムのようにも思います。前作とは違う方向性ですが、何か心境の変化があったのでしょうか?
出戸:踊らせるっていうのは基本的に考えてなかったんですけど、ミニマルな音楽ってダンスの要素も内包しているかもしれないですね。
清水:ダンスミュージックを作ろうっていう意識はなかったと思います。
-前はバンドサウンドだったと思うんですけど、今回はリズムマシンを使っている曲もありますね。
出戸:今回は欠落感というか肉体性のない感じに結果的になったんですけど、無意識的にそういう部分を狙っていたところはありますね。リズム隊がミニマルにループを繰り返している無機質的な感じの上にメロウなものをのせるっていう、相反するものが同時に鳴っているような。
―最初からそういうコンセプトだったんでしょうか。それとも作っていく中で肉体性のないものになったんですか。
出戸:音的にミニマルでメロウなものをやろうって話してて、それがどんなふうになるのか分からなかったけど、結果的に自分達で聴いてみたら肉体性がないものになったっていう感じですね。
-今回のアルバムはメロトロンをはじめ、アナログな楽器を多数使われているようですね。今では手に入りにくい楽器も多いと思いますが、どうしてこれらの楽器を使われたのでしょうか。
出戸:メロトロンを使っているっていうと、サンプリングされたパソコン上の音を使っていることも多いんですが。エンジニアの中村宗一郎さんがビンテージの楽器を沢山所有している人で、オウガのツアー中のことなんですけど、ある街で偶然メロトロンを発見したんですよ。それを使わせてもらって。
清水:今回に限らず、『homely』より前からビンテージの楽器は使っていたと思うんですよね。今回はとりわけ沢山使ったし、何を使ったか明かすのも面白いかも、って話になって。
出戸:リストを載せておくと、興味がある人は音を想像しやすいかなと。フェティッシュというか、楽しいじゃないですか。
-アルバムタイトル『ペーパークラフト』にはどういう意味があるのでしょうか。
出戸:表面だけがキレイに整っていて、裏はペラペラで何もないっていうイメージがアルバムのコンセプトを考えているときにずっと浮かんでて。ジャケットはレコーディングが終わる頃になって描き始めたんですけど、『ペーパークラフト』っていう言葉自体はその時に出てきました。
-今回のジャケットはご自身で作られたそうですね。前作からジャケットも作られるようになったと聞きましたが、どうして自分で作ろうと思ったのでしょうか。
出戸:いい作家さんとか作品を探すとかして、フィーリングの合う人とやっていくバンドが多いかと思うんですけど、ピンと来る人がいなかった。あと自分でもやれそうだなっていうのもあって。
清水:発注するとズレが生じる可能性もあるし。
出戸:向こうも作家さんなので、そのズレを言いづらいのもあって。でもしっかりコンセプチュアルにいこうと思ったら、もちろん曲や詩とかアートワークなんかの、全てのピースがカチっとはまってなきゃならないですよね。例えばジャケットで違うニュアンスが混じり込んじゃうと、全く別の物に転んでしまう危うさもある。繊細にやろうと思うと、他の人と詰めるっていうのが作業的にかなり大変だと思ったので。自分たちでやると時間はかかるし大変だけど、やってみたっていうところです。
-芸大出身だそうですし、もともと絵を描かれていたから自分でやろうって考えもあったのでしょうか。
出戸:それもありますけど、今回は試行錯誤してでも自分たちでやった方がいいかと思いました。やっぱり微妙なニュアンスって言葉で伝えきれないので。
清水:今までもバンドのTシャツとか、出戸君が描いたのも沢山あります。特に芸大出身だからっていうわけでもなく、バンドにまつわるデザインはずっと自力でやっていたんですよ。あと、出戸くんの絵を使ってデザインする作業は自分がやりました。自分も元々美術系なので。
-ジャケットやアー写、PVも作られていますよね。音と、音の外にまつわる表現をできる限り自分たちで詰めたかった作品なのかなと思いました。どうしてそこまで自分達の世界観を凝縮しようとしたのですか?
出戸:今ってitunesとかiphoneみたいにデジタルで聴く人も多くて、それって完全にジャケットのサイズとか質感とかと切り離されてるじゃないですか。普段僕らが音楽と接してる時って、レコードにしてもCDにしても、ジャケットとかアートワークありきで聴いてたりとか、音楽的な体験がそういうものと切り離せないんですよ。
清水:僕らもよく話すんですけど、いま音楽って、iphoneでYouTubeに繋げば、興味を持った瞬間に検索して聴けたりしますよね。だけど10~20年前って、音楽を聴こうと思ったら、レコード以前にまずどんなプレーヤーを買おうとか、じゃあスピーカーはどうするんだとか、そういうモノが音質というか音楽体験を左右してて。アートワークで言ったらジャケ買いって言葉があるくらいだし、モノと音楽が密にリンクしてたと思うんです。音楽を聴くって、フェティッシュな行為だったと思うんですよ。今はそういうこだわりがどんどんなくなってる。それがダメとは思わないんだけど、手軽でまさに「ムダがない」と思うし(笑)。だけど僕らは結局レコードを買っちゃうし、ステレオなんかも自分の気持ちいい機材をいつも探してたりするんです。ライブもほぼ全てビンテージ機材でやっているんですけど、音楽に心地よさとか格好良さを求めると、自然とフェティッシュになってしまうんですよね。そういえば出戸くんの「ムダが無い〜」のPV撮影、あれも一種のフェティッシュな行為かもしれませんよね。デジタルでやってるけど、行為自体はすっごくアナログというかアナクロで。
-撮影はずいぶん時間かかったんですよね。5000枚くらい撮ったって聞きました。
出戸:5000〜6000枚くらい撮りました。写真1枚撮って、ちょっと動かしてまた撮って。延々とその繰り返しで、大変といえば大変でしたね。でも一度はやってみたかったんですよね。たまたま合いそうな曲ができて、イメージもわいたので、やってみようかなって。子どもの頃からやりたかったことが一個やれたかな。
-やってみてどうでした?
出戸:大変というか…まぁしばらくはやらなくていいですね(笑)。
清水:レコーディング終わった直後に、通常盤にピクチャーブックを付けることを思い立って、急遽もう7、8枚くらい絵を描いてよ、って話になったんです。出戸くんが締め切りギリギリまで集中してざーっと描いて、終わった瞬間にPVを作り始めるっていうかなりタイトなスケジュールだったんですよ。公開したのが先週の金曜(10月11日)でしたけど、木曜の深夜まで作っていました。直前まで「ヤバい間に合うのか」ってやっていて。
-ピクチャーブックを見て、作品を聴くとまた発見があるっていう楽しさがあると思います。
清水:去年の春までVAPっていうメジャーレーベルにいて、その後1年間どのレーベルに所属するか迷ってる期間があったんです。VAPで続けることもできたと思うんですけど、新しい所も探したりもしてて。最後の方で『見えないルール』っていう12インチができたんですけど、1年くらい何のリリースもない空白期間があったんです。その間に、活動の細かい部分まで自分たちで全部コントロールして、抜かりなくやってみようって話になって。今年の途中からは、ライブのマネジメントも全部自力でやることになった。結果として、トータルで作り込める形でバンドにまつわる全てがやれてる。そんな流れの中、結晶化されたのが『ペーパークラフト』のような気がします。
-なぜメジャーを辞めてP-VINEに変わったのでしょうか。
出戸:音楽性が『homely』(2011年9月)の発売以降に変わったっていうのがあって。その頃、呼んでもらったイベントで、例えば2000人とか3000人のお客さんの前でやっても、全然誰にも届いてないのでは?って感じるようなライブが何度もありました。メンバーも替わったし、自分たちの演奏がまだまだだったのかもしれないけど、『homely』以前に属していた界隈に違和感を感じることも少なくなかったんです。まあ、相変わらず気にしないで、やりたいことをやってはいたんですけど。そんな中で、ROVOっていうバンドが去年の5月に野音(日比谷野外音楽堂)でやってる名物イベントに呼んでくれたんです。そこにも2000人くらいお客さんがいて、そのお客さんのほとんどが僕らの事を初見だったんですけど、すごく良い感じでやることが出来た。やりたいことを思いっきり攻める形でやって、すごく反響があった。想像はしてたけど、こういう人たちの前でやったらお互いいい感じなんだな、って体感することができたっていうか。今年フジロックのホワイトステージもとても良かったけど、同じ意味です。そういう体験を重ねるうちに、うまく言えないけど活動する環境を見つめ直したというか。今のレーベル(P-VINE)は、ある意味マニアックなんですよ。そういうリスナーの事も解っているような感じがある。だから今のモードには合っているんだと思います。担当の柴崎くんも音楽への愛情があるんだなって、以前から思ってた人だったし。
清水:リリースについて、完全なセルフプロデュースも考えたり、逆にメジャーの毛色が違うところと交渉するっていうのも選択肢にはあったけど、なんか自然にP-VINEに落ち着いたね。
出戸:しっかり話してみてフィーリングが合わなかったらダメだろうな思ってたけど、実際に話したら「わかってるな」という感じがしました。もちろんこれが最初だから、全てをわかったわけではないですが。
-オウガにとって『homely』はとても大事なアルバムなのではないかと思います。あのアルバムをリリースした前後では、楽曲の雰囲気もかなり変わったと思いますが、何かきっかけがあったのでしょうか。
出戸:『浮かれてる人』の前までは、バンドのジャムセッションで曲を作っていて。そういう方向で作っていくには、4人が全く同じことを考えていれば楽しいかもしれないけど、1人でも違うことを考えだすと曲作りが成立しなくなってくるんですよね。4人のちっちゃい輪の中で重なった部分がこれだけだとしたら、これだけの中で曲作りをしなきゃいけない。その時はアルバムを3枚くらい出していたんですけど、どんどん煮詰まっていく感じもあったんですよ。なので、ミニアルバムの『浮かれてる人』で、曲を僕と馬渕がそれぞれ作るようにしよう、コードとか構成を用意したうえでバンドに持っていこうってことにした。そうやってまず土台の作り方が変わったんです。結果としてセッションで作ってた頃よりも、レコーディング作業をやる段階で、バンドアンサンブルが決まってない部分がたくさんあるようになったんですね。そういう変化があって、プロデューサの石原さんも、大きくアレンジする隙があるって思ったんじゃないかなと。あとは人間関係というか、エンジニアの中村さんと石原さんと、バンドが顔なじみになって、言いたい事を言いやすくなったのもこの頃で。こんなアレンジはどう?とか、こういう機材使ったらどう?とか、いろんなやりとりが出来るようになってきたんです。そこからスタジオワークのやり方が前と全然変わった。それまではライブでやって来たことをCDに落とし込む、それにちょっと上乗せするっていうくらいだったんだけど。今はライブとCDは完全に別ものだって思ってます。『homely』はそれが解った最初のアルバムですね。