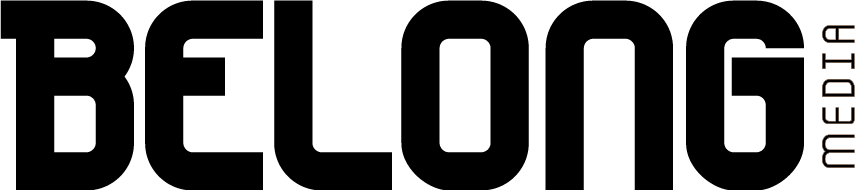最終更新: 2020年8月17日
Washed Outインタビュー

アーティスト:Ernest Greene(Vo.) インタビュアー:Yabori 翻訳:Yada Mayumi
-今回のアルバムは一枚が一つのストーリーを伝えるようなまとまりのある作品だと思いました。今作はまとまりを意識して作ったのでしょうか?
Ernest Greene:その通り。今回のアルバムの最初と最後には、僕がマイクを家の外に置いて拾った音が入ってるんだ。僕にとってはそういうのどかな、戸外の牧歌的なフィーリングがすごく重要だったから。そこは去年、僕が街中からジョージア州アセンズのなんにもない田舎に引っ越したことが大きいと思う。そこがこのアルバムの大きなインスピレーションになったんだよ。制作中、ずっと鮮やかな色が頭にあったんだ。花々や自然……音楽的なアイデアも、そういうものをどうすれば音として表現できるか、サウンドスケープとして描けるか、考えるところから生まれてきた。たとえば、僕にとってはよく晴れた春の日は……きらきらしたハープの音、鈴の音みたいなヴィブラフォンのサウンドだったりする。あったかくて気持ちいい音だね。そういう雰囲気をアルバム全体に持たせたかったんだ。楽観的な感じで、メジャーキーで、聴いていてすごく気持ちいいものにしたかったんだよ。
-今作にはメロトロンやチェンバリン等の50種類もの楽器を使用されたそうですが、どうしてこれほどに多くの楽器の音を入れようと思ったのですか?
今作のアイデアとして、もっと多彩な楽器を使おうとして……そこからいろんなサウンドを試しだして、それが新作のサウンドになっていった。アコースティック楽器、オーケストラ的なサウンドの楽器、ストリングスがたくさん入ってるんだ。今でも基本的には一人でコンピュータで作業してるし、ドラムやベース、時々はギターみたいな楽器のパートを自分で書いてる。ただ、そこが新作で一つ違うところなんだけど、今回はそういうやりかたを変えようと思ったんだ。これまでになくコンピュータに頼らず楽器を演奏したし、その意味では音楽的にかなり変わったと思う。僕は同じようなアルバムを繰り返し作りたくないし、つねに新しいテクニック、新しいやりかたで実験したいと思ってるから。
-色んな楽器が入っているだけにライブでの再現が大変だと思うのですが、今作をライブでどう表現しようと思いますか?
そこはやっぱりすごくエキサイティングだし、イライラさせられるところでもあるんだよね。プログラミングしたサウンドで言えば、コンピュータを使えばフレキシブルにやれるから、融通がきくんだけど……実際、キーボードとサンプラーでアルバムをそのまま再現することもできる。バンドとしては僕がキーボードとパーカッション、ちょっとだけギターを担当してて、ドラムがいて、ベーシストがエレキのベースとアップライトのベース、シンセベースを弾くんだ。で、ギターがエレキギターとシンセ、パーカッションもちょっと弾く。だから、ちょっと削ぎ落としてるとはいえ、アルバムをほぼ再現できるし、テクノロジーを使ってアルバムに入ってるエキゾチックなサウンドも入れられるんだよね。うん、ビートルズがキャリアの後半でツアーをやらなくなったのは、アルバムの音を再現できなくなったからだよね? ビートルズでさえライブではうまくやれないと思ってた。80ピースのオーケストラとか。でも最近のコンピュータ・テクノロジーでは、そういうかなりドラマチックなこともやってしまえる部分があるんだ。
-前作と比べてリズム隊の音がよりはっきりした曲が増えたように思います。それをしようと思ったのはどうしてでしょうか。
もちろん。そこもライブをかなりやったことから生まれた部分だと思う。ライブではいいグルーヴって重要だし、僕らの初期のパフォーマンスを聴くとすごくこわばってるんだよね。実際、エレクトロニック・ミュージックにはそういうこわばった、堅い感じのものが多いと思うし、コンピュータやドラムマシンを使うとどうしても正確になりすぎる。反復的な音楽をライブで演奏するのってすごく難しいんだよ。四人の人間がステージに上がってるのに、ドラムマシンとかシーケンスを使うとものすごく四角四面な感じになってしまう。ルーズで人間的なフィーリングがある曲のほうがライブではうまくいくんだよね。だから今回のアルバムでは、意識的にそういう曲を増やすようにした。きちんと聞こえすぎる部分を減らして、ルーズなグルーヴ、フィーリングを増やすようにしたんだ。最初から最後まできっちりテンポが同じじゃなくて、もっと自然な、人間的なグルーヴにしたり。そこは確実に意識的だったね。タンバリンやパーカッションのサウンドもたくさん入ってるし。
-プロデューサーは前作と同じベン・アレンを起用しているそうですが、彼を起用した理由について教えてください。
彼はオールドスクールな録音技術に熟達していて、マイクの位置やサウンド・エンジニアリングに通じてる。僕は最初、そういうことに関してまったく無知だったんだよ。ただ彼に自分が欲しいものを伝えることはできるから、頭の中で鳴ってるサウンドを話して、彼が技術的なノウハウでそれを形にしてくれる。あと彼自身ミュージシャンとして才能があるから、僕がすごく曖昧で抽象的なことを思い付いても、それをちゃんと解釈してくれるんだよ(笑)。僕の両方のアルバムで楽器もいろいろ演奏してて、実際僕よりミュージシャンとして技術的なところではずっと才能がある。だから僕がある楽器のパートを思い付くと、自分で弾く前に彼がぱっとやってくれることも多いんだ。僕がやったら30分はかかるところを、彼なら2分でできる。その意味でも彼と組むのはすごくうまくいくんだよ。
-今作のタイトルの「パラコズム」は心理学的に現実を拒絶するネガティブなタイトルだそうですが、この言葉をポジティブに使おうと思った背景について教えてください。
このタイトルを付ける前に、僕の頭にあったのが……一つの場所っていうか。僕にとってこのタイトルはデイドリーム=白日夢、空想を表す言葉なんだよね。ゆっくり目を開くと、突然自分がまったく違う場所にいるのに気付く感じ。理想的な場所っていうのかな。“イット・オール・フィールズ・ライト”がまさにそれを表してるんだけど、あの曲はすべての物事がぴったり当てはまるような瞬間、全部が完璧に思えるような美しい瞬間について歌ってるんだ。僕にとってはそれこそが『パラコズム』のアイデアなんだよ。アルバムを聴いている45分間、ずっと夢の中にいるようなね」。
チルウェイブへの違和感

-あるメディアの取材で100%逃避主義を受け入れると言い切ったそうですが、あなたがそう考えるようになったのはどうしてでしょうか。
だって、逃避主義はウォッシュト・アウトの大きな一部なんだよ。さっきも言ったけど、ある種のノスタルジアや想像力は日常から一歩離れるのにすごく重要だと思う。あと、ユニークであるためにも大切だよね。一人ひとり、夢って全然違うはずだから。うまく言えないけど、僕にとって音楽が素晴らしいのは、聴く人を違う場所へ連れていってくれるところなんだよ。ある意味、すべてのアートがそういうものなんだけど……僕は曲を聴いて、すぐに今いる場所とは違うところへトランスポートされる気持ちになることがある。ボーズ・オブ・カナダの音楽を聴くと過去へ引き戻されるような感覚になるしね。自分の過去のどこかの瞬間でなくても、何かしら懐かしい気持ち、ノスタルジアに襲われるんだ。そこにものすごくインスパイアされる。だから、エスケーピズムに関しては完全に肯定派だね(笑)。
-以前あなたの楽曲をリミックスしたスター・スリンガーにもインタビューしたことがあるのですが、彼との作業はいかがでしたか?
彼とは一緒にツアーしたんだ。すごいと思う。みんなヒップホップのことをシンプルな音楽として語ることが多いんだけど……当然反復的な音楽なんだけど、テクニカル側面から言うと難しかったりもするんだ。ベースがヘヴィな音楽って、うまく作るのがすごく難しい。でもその意味で彼のプロダクション・スキルには驚かされるし、サウンドのクオリティがすごく高い。彼のパフォーマンスを大きなフェスでも観たんだけど、あれだけ巨大なサウンドシステムだと、きちんとプロデュースされた音楽じゃないとうまくいかないんだよね。でも彼の曲は大きなサブスピーカーで聴くとすっごくいいサウンドだし、彼にウォッシュト・アウトのリミクスをしてもらったのは嬉しかった。新作を楽しみにしてるんだ。
-あなたの楽曲には「BELONG」という曲がありますね。あの曲はどういったことを歌っているのですか?
あの曲は僕にとってすごく重要な曲なんだよ。当時、僕は大学の後どうするのか、より普通の道がクリアに見えてた。ある意味僕の前にレールが敷かれてたしね。でも音楽のほうでもいろんなことが起きはじめてて、でもそれは僕にとってよりリスキーな選択、普通じゃない道だったんだ。自分ではその二つの方向に引っ張られてるみたいに感じてた。音楽制作を仕事にして、冒険するのはものすごく魅力的だったんだけど、やっぱり失敗するかもしれないっていう恐怖もあったから。結婚したばっかりで、二人の生活を安定させたい気持ちもすごくあったしね。あの曲はその押し引き、自分はどういう人間で、どういうステップを進めばいいのか考えてることを歌ってるんだ。奇妙な時期だったんだよ。うん、正しい選択をしてたらいいんだけど。9時5時の仕事に就いてたら、今よりハッピーだったかもしれないし、もっと惨めだったかもしれないね(笑)。
-以前インタビューであなたがクラブやレイヴに行かないと聴いて、とても納得してしましました。かく言う自分もクラブには行かないからこそあなたの音楽に共感できるのだと思います。クラブに行かないのはどうしてでしょうか?
僕の出身地ではダンス・カルチャーがそんなになかったんだ。ダンス・ミュージックは聴いてたけど、部屋で一人、ヘッドフォンで聴いたりしてた。イギリスのマンチェスターとか、ダンス・ミュージックがすごく重要な場所で育ったキッズとはそういう音楽との関係性が全然違ってたんだ。若い頃からクラブに通ってたら、僕の聴きかたとは全然違うだろうし。だから僕としては、ダンス・ミュージックやヒップホップからアイデアを得て、それをヘッドフォンで聴くような音楽、もっとパーソナルな音楽に当てはめてたんだと思う。だから僕からすると、レイヴでウォッシュト・アウトの音楽が鳴ったらすごく変な気分になるだろうし(笑)、大体うまくいくとも思えない。ダンスのテンポでもないからね。
-チルウェイブというジャンルで呼ばれる事に対してどう思いますか?
ちょっと変な気持ちだな。当然、音楽ジャンルを作ろうとか、ムーヴメントを起こそうとして始めたわけじゃないから。僕自身かなりいろんな音楽を聴くし、幅広いジャンルからアイデアを得てると思う。ただ意識的に、何かのジャンルに当てはまるような曲を書こうとすることはないんだ。ただ、そういうふうになったこと自体は幸運だったと思ってる。同じようなことをしてる大勢と比べて、結果的に僕を際立たせることになったから。それは感謝してるんだ。そう、今回のアルバムはチルウェイヴがリプリゼントするものに対する反動なのかってよく訊かれるんだけど、僕自身は全然それはなかったと思う。僕としてはずっとやってきたこと、ウォッシュト・アウトの他のレコード全部にある同じアイデアを取り上げて、それを形にするのに違う楽器、違うアプローチを取っただけなんだよね。やっぱり、ウォッシュト・アウトのアルバムになってると思う。